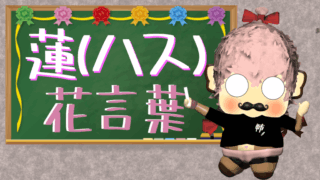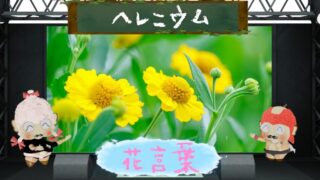コピーライターで花屋の元店員です。この記事では、ハギと花言葉について詳しく解説します。日本文化に深く根付いた植物である萩(ハギ)は、古典文学や秋の七草にも登場し、精神や思案を象徴する花言葉を持ちます。ここではハギの花の魅力、使い方、スピリチュアルな側面まで幅広く取り上げます。
ハギとは?基本情報

- 学名:Lespedeza 属
- 科名:マメ科
- 原産・分布:日本を中心に東アジア一帯に自生
- 開花時期:7月〜10月
- 特徴:しなやかに枝垂れる枝に小さな蝶形の花をたくさんつける落葉低木。赤紫、白、ピンクなどの花色があり、風に揺れる姿が美しいです。
良さ・魅力
- 秋の七草の代表
秋を象徴する植物として万葉集に多く詠まれ、季節感を最も伝える花のひとつです。 - 控えめな美しさ
小さな花が枝垂れて咲く姿は大輪にはない繊細さがあり、日本人の美意識「わび・さび」を表す存在とされています。 - 四季の変化を楽しめる
春の芽吹き、夏の青葉、秋の花、冬の枝ぶりと、一年を通して風情を感じさせてくれる庭木です。 - 日本庭園との調和
野趣を漂わせつつ、茶庭や寺院の庭にもよく合い、侘びた風景を演出します。 - 実用性もある植物
根や葉に薬効があるとされ、民間療法で使われた歴史もあります。
ハギの花言葉

- 思案
萩の枝が細くしなやかに揺れる姿が、まるで物思いにふける人のように見えることから生まれた花言葉です。秋のしみじみとした雰囲気と重なります。 - 柔軟な精神
枝がしなやかで折れにくい特徴から、困難に対しても柔らかく受け止める心を象徴します。 - 想い
万葉集や古典文学で、萩は恋心や人を想う気持ちと結びつけられて詠まれることが多く、そこから「想い」「恋の思案」といった意味が込められています。 - 内気
小さな花が控えめに枝垂れて咲く様子が、主張しすぎない内気さや奥ゆかしさに重ねられています。
文化とのつながり
- 秋の七草に数えられることから、萩は「移ろう季節を想う花」として特別視されました。
- 万葉集では恋や哀愁を詠む題材として頻繁に登場し、花言葉「思案」「想い」の背景となっています。
- 控えめに咲く姿から、昔から「強く自己主張せず、相手を想いやる心」を象徴する花とされてきました。
花言葉を知ると、萩の「儚さ」と「しなやかな強さ」の両方がより深く感じられますね。
ハギの花言葉~色別ver

赤紫の萩(もっとも一般的な色)
- 花言葉:「情熱的な想い」「愛の告白」「移ろう恋心」
- 由来:赤紫は古来より高貴な色とされ、華やかさの中に憂いを感じさせることから「恋心」や「情熱」と結びつきました。万葉集でも萩は恋の歌に多く詠まれています。
白い萩
- 花言葉:「思いやり」「清らかな心」「内気」
- 由来:白い小花が楚々と咲く姿から、純粋さや奥ゆかしさを象徴します。派手さがなく、控えめな美しさを持つことから「内気」という意味も加わりました。
ピンクの萩(園芸品種に多い)
- 花言葉:「優しい心」「繊細な想い」
- 由来:柔らかなピンクは温和さや女性らしさをイメージさせ、人を思いやるやさしさを花言葉としています。
濃い紫の萩(シロバナや園芸品の変種)
- 花言葉:「深い愛」「静かな思索」
- 由来:濃い紫は精神性や高貴さを象徴し、静かに深い愛情や思考を重ねる姿と重ねられています。
総合的な意味
色に関わらず、萩全般の花言葉は「思案」「柔軟な精神」「想い」に集約されますが、色ごとに「恋」「清らかさ」「やさしさ」「深い愛」といったニュアンスが加わるのが特徴です。
ハギの花言葉の由来

1. 「思案」「想い」
- 由来:枝が細くしなやかにしなだれて、風に揺れながら小さな花を咲かせる姿が、物思いにふける人の姿に重ねられました。
- 文学的背景:万葉集では萩が最も多く登場する花で(140首以上)、恋の歌や別れの歌に多く詠まれたことから「想い」「物思い」に結びついたと考えられます。
- 例:「萩の花 うつろふ色に 秋風の 吹きてしをれば 恋ぞまされる」
2. 「柔軟な精神」
- 由来:萩の枝はとても柔らかく、風に揺れてもしなやかに受け流し、簡単には折れません。その性質が「困難にも折れない心」=柔軟な精神を象徴しました。
- 日本文化との関わり:これは「柳に風」と同じ発想で、日本人が好む「しなやかに生きる美徳」を表す花言葉になりました。
3. 「内気」
- 由来:萩の花はとても小さく、控えめに枝垂れて咲くため、大輪の花のように自己主張はしません。その姿が「奥ゆかしい」「控えめ」「内気」というイメージにつながりました。
- 美意識との関係:日本人の「わび・さび」の感覚とも結びつき、派手ではなく楚々とした美しさが評価されています。
4. 「恋心」「移ろいやすい愛」(赤紫の萩)
- 由来:萩は咲き進むとすぐに花が散り、儚さを感じさせます。その様子が「移ろいやすい恋心」と重ねられ、恋の花として詠まれました。
- 文学背景:源氏物語や古今和歌集などでも、秋の萩は恋の象徴として描かれています。
由来まとめ
萩の花言葉は、
- 姿(しなやかさ・控えめさ・儚さ)
- 古典文学(恋や哀愁を詠んだ和歌の題材)
- 日本人の美意識(わび・さび、柔らかさ)
この3つが合わさって生まれました。
ハギの花言葉は怖いの?

ハギ(萩)の花言葉に「怖い」意味はありません。
むしろ、萩は秋の風物詩として「しなやかさ」「物思い」「恋心」といった優しい意味が多い植物です。
ただし「花言葉=怖い」というイメージは、曼殊沙華(ヒガンバナ)や黒い薔薇のように、死や別れに関連する花と混同されることがあるので、ここで詳しく整理しておきます。
「怖い」と誤解される理由
- 秋の野辺の寂しさ
萩は秋の七草に数えられますが、派手さがなく小花が儚げに散るため、寂しさやもの悲しさを連想させることがあります。そこから「怖い花言葉があるのでは?」と誤解されやすいです。 - 曼殊沙華(彼岸花)との混同
秋の花として彼岸花と並んで思い浮かべる人も多く、彼岸花には「死」「情熱」「再会」といった少し怖い意味が含まれるため、混同されるケースがあります。 - 古典文学の表現
万葉集や源氏物語で萩は「別れ」「物思い」に重ねられて詠まれることが多く、そこから「憂い」や「切なさ」を「怖い」と感じる人がいるのかもしれません。
怖いのは誤解
- 萩の花言葉に「怖い」意味はない
- 主に「想い」「思案」「しなやかさ」「恋心」といった柔らかい意味が中心
- 「怖い」と誤解されるのは、儚さや彼岸花との混同が原因
ハギ(萩)を詠んだ和歌と花言葉

① 万葉集(山上憶良)
「秋の野に 咲きたる花を 指折りかき数ふれば 七草の花」
(意味:秋の野に咲く花を数えてみると、七草があるよ)
➡ この歌で萩は 「秋の七草」 の代表として登場します。
秋を象徴する花として古代から親しまれ、そこから「思案」「想い」といった花言葉が広まりました。
② 万葉集(大伴家持)
「萩の花 咲きたる野辺を 行きめぐり 見つつ偲はな 妹があたりを」
(意味:萩の花が咲いている野辺を歩きながら、愛しい妻の面影を偲んでいる)
➡ 萩の花が「恋しい人を想う心」と結びつき、花言葉 「想い」「恋心」 の由来となっています。
③ 古今和歌集(紀貫之)
「秋風に たなびく雲の 絶え間より もれ出づる月の 影のさやけさ」
(萩そのものは直接登場しませんが、この歌が詠まれた情景とともに、萩と月はしばしば組み合わされて描かれました)
➡ 萩と月は古典文学でよく取り合わせられ、「物思いにふける」情景を強める要素となり、花言葉 「思案」 とつながっています。
④ 花札の「萩に猪」
江戸時代以降、萩は花札にも描かれています。猪が萩の群れを駆け抜ける様子は「野趣あふれる秋」を表現。
➡ これは花言葉の「柔軟な精神」に重なり、萩が折れずに揺れる姿が、自然の厳しさにも耐えるしなやかさを象徴しています。
⑤ 松尾芭蕉(俳句)
「山路来て 何やらゆかし すみれ草」 と同じく、芭蕉は萩を題材にした句も多く残しました。代表的なものは:
「白萩や 風に散りしく 夜の雨」
➡ 白萩が風に散って雨に濡れる情景は、儚さや内気な印象を与え、花言葉 「内気」「清らかな心」 を裏付ける表現といえます。
文化とハギの関係性
- 万葉集 → 恋や人を想う気持ち → 「想い」「恋心」
- 源氏物語や古今和歌集 → 月や風との組み合わせ → 「思案」「物思い」
- 俳句や花札 → しなやかさや儚さ → 「柔軟な精神」「内気」
こうして日本文化の中で繰り返し詠まれ、萩の花言葉が形づくられてきたのです。
ハギの面白いエピソード

- 万葉集で最も多く詠まれた花
萩は万葉集に140首以上も登場し、当時の人々に最も愛された花でした。 - 源氏物語に登場
「夕顔」の巻などで萩と風の組み合わせが描かれ、文学的にも秋の象徴とされています。 - 萩寺と観光
京都の常林寺、奈良の新薬師寺など「萩の名所」とされる寺院があり、秋には観光客で賑わいます。 - 花札の「萩に猪」
花札の図柄に登場し、季節感と野趣を象徴する存在として日本文化に深く根付いています。 - 名前の由来
「はぎ」は「生え芽(はえぎ)」が語源とされ、新しい芽吹きを意味しているという説があります。
ハギの花の魅力と使い方

萩(ハギ)はマメ科の落葉低木で、学名はLespedeza。属名は「Bush Clover(ブッシュクローバー)」とも呼ばれ、種類も多様です。日本の山野に自生し、ヤマハギやピンク色の園芸品種など、観賞価値の高い植物として親しまれています。花言葉の由来は「思案」「内気」「柔軟な精神」などで、秋の七草の一つとしても有名です。花屋で働いていた頃、萩の枝物は秋のしつらえに欠かせない素材としてよく扱いました。楚々とした姿はアレンジメントや茶花にも映え、控えめながら存在感のある花材でした。
季節と見頃
ハギの開花時期は夏から秋にかけてで、特に見頃は9月前後。誕生花としては9月に割り当てられることが多く、季節感を強く演出します。日本の古典では、秋風とともに揺れる萩の枝が数多く詠まれました。花屋の現場でも「秋らしいアレンジが欲しい」と言われると、萩を合わせることが多く、控えめなピンクや白の花は他の植物を引き立てる役割を果たしました。
しつらえ
萩は切り枝としての利用だけでなく、庭木や茶庭にも重宝されます。枝垂れる姿はしつらえに奥行きを与え、和の空間と調和します。花屋で萩を生ける際は、他の秋草と組み合わせることが多く、リンドウやススキと合わせると「秋の七草」の情緒を再現できます。内気で控えめな印象を持つ花だからこそ、背景や余白を活かす生け方が似合うのです。
贈るシーンとその意味
花言葉の意味から、萩は恋心や思慕の気持ちを伝える植物として適しています。特に「思案」や「柔軟な精神」という花言葉は、相手を大切に思う気持ちを静かに表現します。誕生日プレゼントや秋の節目の贈り物に添えると、落ち着いた雰囲気を演出できます。派手ではない分、内面の深い想いを託すのにふさわしい花だと、花屋勤務時代に感じていました。
スピリチュアルな観点から見るハギ

ハギの花は、古来よりスピリチュアルな象徴とされてきました。日本では秋の七草の一つとして祈りや供養の場にも登場し、精神や心の在り方を映す植物とされています。実際に萩の枝を見つめていると、柔らかく揺れる姿に自分の心も落ち着いていく感覚があります。花言葉に込められた意味は、日常の中で自分を見つめ直すきっかけを与えてくれるのです。
スピリチュアルなメッセージ
ハギの花言葉「思案」「想い」は、心の奥にある静かなメッセージを示します。スピリチュアルな観点では、未来を考え、過去を振り返り、自分の精神を整える象徴とされています。花屋時代、お客様が「控えめで落ち着いた花が欲しい」と選ぶのは萩の枝であり、心の安らぎを求める方に自然と響く植物でした。
心に与える影響
萩の花は内気で小さく、それでいて群れ咲く姿に温かみがあります。見る人に「無理をせず自然体でよい」という安心感を与え、精神をリラックスさせる効果があります。季節の移ろいを告げる植物として、萩は「心を整える役割」を果たしているといえるでしょう。
他の花のスピリチュアルな関係
萩は秋の七草の一つであり、ススキ、リンドウ、オミナエシなどと組み合わされます。これらの植物は、それぞれに精神的な意味を持ち、萩と共鳴します。ススキが「生命力」、リンドウが「誠実」、オミナエシが「美徳」を象徴するように、萩は「思案」「内気」を表します。これらを合わせることで、より豊かなスピリチュアルな調和が生まれます。花屋でのアレンジメントでも、こうした組み合わせは人気でした。
ハギの他は?日本で人気の花々
日本で人気の高い花を10個、それぞれの良さを含めてご提案します。
1. チューリップ
春の代表花として世界中で愛されるチューリップは、鮮やかな赤や黄色、やわらかなピンクなど種類豊富な色彩が魅力です。品種改良も盛んで、八重咲きやフリンジ咲きなどバリエーションも豊か。花言葉は色ごとに異なり、赤は「愛の告白」、黄色は「望みのない恋」と切なさを含みます。入学や新生活の時期にふさわしい花で、花壇や切り花として人気です。
2. 薔薇(バラ)
「花の女王」とも呼ばれる薔薇は、日本でも絶大な人気を誇ります。豊潤な香りと華やかな姿は贈り物に最適で、花束やアレンジメントの中心に使われます。花言葉は赤が「情熱」、白が「純潔」、ピンクが「感謝」と幅広く、想いを伝える花として定番。母の日やプロポーズなど、特別なシーンを彩ります。
3. 桜
日本の春を象徴する桜は、短い開花時期に人々を魅了します。花言葉は「精神の美」や「優美な女性」。淡いピンクの花びらが舞う光景は、日本文化や詩歌に数多く登場します。公園や街路樹として広く植えられ、お花見を通じて人と人を結びつける存在でもあります。
4. 紫陽花(アジサイ)
梅雨の時期に彩りを添える紫陽花は、青や紫、ピンクなど花色が土壌の酸度によって変化する特徴を持ちます。花言葉は「移り気」「家族団らん」。雨に濡れた姿も美しく、庭先や寺社に多く植えられています。和の雰囲気にも洋の雰囲気にも馴染む人気の花です。
5. 向日葵(ヒマワリ)
夏を象徴する花で、太陽に向かって咲く姿が印象的。明るい黄色が人々に元気を与えます。花言葉は「憧れ」「情熱」「あなただけを見つめる」。切り花としても日持ちが良く、贈り物にもぴったりです。子どもから大人まで広く愛される花です。
6. 菊
日本の伝統を象徴する花であり、皇室の紋章にも使われています。秋に見頃を迎える菊は「高貴」「高潔」などの花言葉を持ち、格式高い印象を与えます。長持ちするため仏花やお供えに用いられる一方、洋風のアレンジメントにも取り入れられています。
7. 梅
早春に咲く梅は、寒さに耐えて美しい花を咲かせることから「忍耐」「高潔」といった花言葉を持ちます。白梅は清楚さ、紅梅は華やかさを感じさせます。香り高い花は観賞用としても人気で、日本庭園や盆栽にもよく見られます。
8. 蓮(ハス)
夏の朝に水面に咲く蓮は、清らかさと神秘性で人々を魅了します。仏教とも深い関わりがあり、花言葉は「清らかな心」。池や水鉢で育てられ、静寂と美を象徴します。写真映えする美しさもあり、観光名所にも多く植えられています。
9. 椿
冬から春にかけて咲く椿は、艶やかな花びらと濃い緑の葉が特徴です。花言葉は「控えめな優しさ」「誇り」。茶道の花としても重宝され、日本文化に根付いた存在です。赤椿は華やか、白椿は清楚な印象を与え、庭木としても人気があります。
10. 蘭(ラン)
高貴で気品ある花として人気の蘭は、胡蝶蘭やカトレアなど多彩な種類があります。花言葉は「幸福が飛んでくる」「美しい淑女」。お祝い事やビジネスシーンで贈られる花の代表格です。長く咲き続けることから、縁起の良い贈り物として重宝されています。
まとめ
ハギは日本文化に深く根差したマメ科の植物であり、学名はLespedeza。属名はBush Cloverとも呼ばれます。自生する種類は多く、ヤマハギや園芸用のピンク色の品種など、バリエーションも豊富です。開花時期は夏から秋で、特に9月が見頃。誕生花としても親しまれ、秋の七草の一つとして日本人の心に刻まれています。
花言葉は「思案」「内気」「柔軟な精神」「恋心」などで、その由来は植物の姿や文学的背景にあります。スピリチュアルな観点からも、萩は心を整え、精神を落ち着かせる花。贈り物やしつらえにおいて、控えめながら大きな意味を持つ花だと言えるでしょう。
これから秋の季節を迎える際、ぜひハギの花と花言葉を思い出し、暮らしに取り入れてみてください。静かに心を支えてくれる一輪になるはずです。
ライター紹介 Writer introduction
Sato君
花屋で働いてた日本男児(O型) コピーライターの経験も活かし花に関して、わかりやすく&信ぴょう性がある記事作りを心掛けながら配信中。 instagramでは「動く!4コマ漫画~花言葉劇場」を投稿しています。