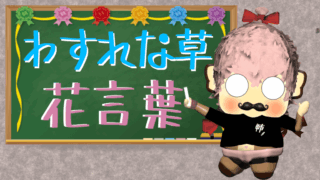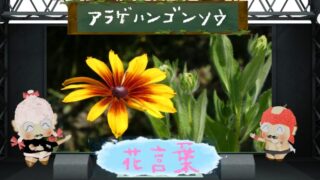コピーライターで花屋の元店員です。今回は秋に咲く美しい花「彼岸花」の花言葉や由来、宗教的背景、毒性、文化、贈り物としての意味まで詳しく解説します。彼岸花(ヒガンバナ)は曼珠沙華(まんじゅしゃげ)とも呼ばれ、日本や中国の文化に深く根付いた植物であり、花言葉の意味や背景には神秘的な要素が多く存在します。この記事では、花屋での経験を踏まえ、色別の特徴や見頃、誕生花としての魅力、プレゼントの際の注意点まで詳しくお伝えします。
彼岸花とは?基本情報

- 和名:彼岸花(ひがんばな)
- 別名:曼珠沙華(まんじゅしゃげ)、死人花、狐花
- 学名:Lycoris radiata
- 科名:ヒガンバナ科
- 原産地:中国
- 開花時期:9月中旬~下旬(秋の彼岸頃)
- 花色:赤が主流、ほかに白・黄色も存在
- 特徴:花と葉が同時に出ない「葉見ず花見ず」の花で、咲いた後に葉が伸びるという独特な性質を持ちます。
良さ・魅力
- 秋の訪れを告げる風物詩
稲刈り時期の田んぼや土手に一斉に咲く様子は、秋の日本らしい景色として多くの人に親しまれています。 - 自然の防御機能
毒性を持つことから、昔はモグラやネズミ避けとして田畑や墓地の周りに植えられ、農作物や遺体を守る役割も果たしました。 - 神秘的な美しさ
細い花弁が反り返る独特な形と鮮やかな赤色は、どこか妖艶で幻想的な雰囲気を漂わせます。 - 信仰との結びつき
仏教の影響で、彼岸花は「あの世」「輪廻転生」「再会」といった意味を象徴する花として扱われています。
彼岸花(ヒガンバナ)の花言葉

- 「情熱」
鮮やかな赤色と力強い咲き姿から生まれた花言葉。燃えるような強い思いを象徴します。 - 「再会」
毎年お彼岸の頃に必ず同じ場所に咲くことから、再び会えるという意味が込められています。 - 「あきらめ」
花と葉が同時に出ず、互いに会えないことから「叶わぬ想い」を連想させるため。 - 「独立」
田んぼの畔や墓地など、他の花と群れずに咲く姿から来ています。 - 「悲しい思い出」
墓地に多く植えられ、死や別れと結びつくことが由来とされます。
文化や伝承との関係
- 彼岸花はお墓や田んぼの畔に多く咲くため、死やあの世との結びつきが強く、「亡き人への想い」を象徴する花として扱われます。
- 中国では「曼珠沙華(まんじゅしゃげ)」とも呼ばれ、天上の花として仏教とも深い関わりがあります。
彼岸花(ヒガンバナ)の花言葉~色別ver

ヒガンバナ(彼岸花)は色ごとに異なる花言葉を持ち、それぞれに独自の意味や背景があります。以下では、赤・白・黄色のヒガンバナについて詳しく解説します。
赤いヒガンバナ(最も一般的)
花言葉:
- 情熱
燃えるような赤い色から、強く激しい愛情や感情を象徴しています。 - 再会
秋の彼岸に咲くことから、亡き人や遠く離れた人との「魂の再会」を意味します。 - 悲しい思い出
お墓や仏前に供えられることが多いため、死別や過去の哀しみと結びついています。 - 諦め(叶わぬ愛)
花と葉が同時に存在しない「葉見ず花見ず」の特徴から、交わることのない想いや切ない別れを表現します。
白いヒガンバナ
花言葉:
- また会う日を楽しみに
清らかな白色は、穏やかな別れと再会への希望を示します。 - 思うはあなた一人
純粋で一途な愛を象徴しており、赤い花の情熱とは異なり、静かな愛情を意味します。 - 優しさ
白いヒガンバナは赤に比べてやや珍しく、柔らかな雰囲気から優しさや慈愛のイメージが生まれました。
黄色いヒガンバナ
花言葉:
- 深い思いやり
黄色の優しい色合いは、周囲への温かい気持ちや慈しみを表現します。 - 追憶(懐かしさ)
郷愁を誘う色合いから、過去の楽しい日々や懐かしい記憶を思い出させる意味が込められています。 - 元気な心
黄色は陽気な色として、心を明るく保つイメージも含まれます。
色の違いによる印象の変化
- 赤:強い感情・愛や別れに結びつくイメージが強い
- 白:清らかで静かな愛・再会への希望を象徴
- 黄:温かさや郷愁・思いやりを表すポジティブな印象
ヒガンバナはその咲く時期や仏教との関わりから、**「死」「別れ」だけでなく「愛」「再会」**といった相反する意味を持つ特別な花です。
彼岸花(ヒガンバナ)の花言葉の由来

ヒガンバナ(彼岸花)の花言葉の由来は、その生態的特徴、仏教や民間信仰との関わり、そして人々の生活や文化に根付いた歴史から生まれたものです。以下に詳しく説明します。
1. 生態に由来する花言葉
ヒガンバナは「葉見ず花見ず」と呼ばれる独特の性質を持っています。
- 花が咲く頃には葉が枯れており、葉が茂る頃には花は存在しません。
- このため、**「すれ違う存在」「決して交わらない関係」**を象徴し、
→ **「諦め」「叶わぬ愛」**という花言葉が生まれました。
この特徴は、恋愛や人間関係における「出会っても結ばれない運命」を連想させる要因ともなっています。
2. 仏教や彼岸との関わり
ヒガンバナは秋のお彼岸の時期に咲くことから、仏教行事や死者供養と結びついています。
- 「彼岸」とは、迷いや苦しみのある現世(此岸)から悟りの境地(彼岸)へ到達することを意味します。
- 彼岸花はお墓や仏前に供えられることが多く、**「死者との再会」「あの世とのつながり」を象徴。
→ ここから「再会」「悲しい思い出」**の花言葉が広まりました。
また、中国由来の仏典ではヒガンバナは**「曼珠沙華(まんじゅしゃげ)」と呼ばれ、「天界に咲く花」「吉兆の花」**ともされています。
3. 生活習慣や伝承に由来
昔の日本では、ヒガンバナは田畑の畔やお墓の周囲によく植えられていました。
- 球根には毒(リコリン)があり、モグラやネズミから作物を守るために植えられていた。
- また、お墓周りに植えることで野生動物の掘り返しを防ぐ目的もありました。
こうした「お墓」「死」との近い関係から、哀愁や別れの象徴としての花言葉が付与されました。
4. 恋愛や悲しい伝承からの影響
中国や日本の古い伝承では、ヒガンバナは「すれ違う恋人たち」の象徴として描かれることがあります。
- 中国の伝説では、**花を守る妖精・曼珠(まんじゅ)**と、**葉を守る妖精・沙華(しゃか)が恋に落ちますが、神の掟により決して会うことが許されず、花と葉が同時に存在できなくなったと伝えられます。
→ これが「諦め」「悲しい思い出」**という花言葉の由来の一つになりました。
まとめ
ヒガンバナの花言葉は、
- 生態(葉見ず花見ず) → 「諦め」「叶わぬ愛」
- 仏教・彼岸行事 → 「再会」「悲しい思い出」
- 文化・生活習慣 → 「死や供養との結びつき」
- 伝承・神話 → 「すれ違う恋」「悲恋」
これらが複合的に影響して、愛・別れ・死・再会という相反する意味を併せ持つ花言葉が形成されました。
彼岸花の花言葉は怖いの?

ヒガンバナ(彼岸花)の花言葉は一部「怖い」と感じられるものがありますが、それは見た目の鮮烈さや死やお墓との深い関係、そして悲しい伝承が背景にあるためです。以下に詳しく解説します。
花言葉が「怖い」と言われる理由
1. 「死」や「別れ」に関連する意味が多い
- 花言葉には 「悲しい思い出」「諦め」「再会」 などがあり、特にお墓や仏前に供えられる花としてのイメージから「死者とのつながり」を連想させます。
- 「再会」という花言葉も、現世での再会ではなく死後の再会を暗示すると解釈されることがあります。
2. 生態の不思議さ(葉見ず花見ず)
- ヒガンバナは「葉見ず花見ず」と呼ばれる特性を持ち、花と葉が決して同時に存在しないため、「すれ違う愛」や「決して結ばれない関係」の象徴となりました。
→ これが**「諦め」「叶わぬ愛」**という、切なくも不吉に感じられる花言葉につながります。
3. 毒性と古い生活習慣の影響
- ヒガンバナの球根には毒(リコリン)があり、かつては田んぼや墓地に植えて動物よけにされました。
- そのため、「お墓に咲く毒の花」というイメージが強まり、恐ろしい花という印象が広がったのです。
4. 伝承や妖しいイメージ
- 中国の伝説では、ヒガンバナは**「決して結ばれない恋人たちの象徴」**とされ、妖艶で哀しい物語と結びつけられました。
- 日本でも、「墓地に咲く赤い花=不吉」「死者を導く花」といった民間信仰が、花言葉のイメージをさらに怖く感じさせています。
実際の花言葉は「怖い」だけじゃない
一方で、ヒガンバナには**「情熱」「思うはあなた一人」「また会う日を楽しみに」といった愛や再会のポジティブな意味**もあります。
つまり、ヒガンバナは「死」や「別れ」の象徴であると同時に、愛情や魂のつながりを表す花でもあるのです。
怖いのは文化的背景
ヒガンバナの花言葉が「怖い」と感じるのは、
- お墓や死者供養との関係
- 「諦め」「悲しい思い出」といった意味
- 毒性や伝承の影響
といった文化的背景によるものですが、同時に**「愛」「情熱」「再会」**という美しい意味も併せ持っています。
彼岸花の花言葉~本数別ver

実は、ヒガンバナ(彼岸花)自体には本数による公式な花言葉は存在しません。
しかし、日本では古くから「花を贈る際の本数」に意味を持たせる文化があり、バラなどの花と同様に、ヒガンバナにも本数による解釈が応用されることがあります。
以下は、ヒガンバナの花言葉や特徴を踏まえて、本数別に考えられる意味を解説します。
1本のヒガンバナ
- 意味:孤独、独立、唯一の想い
→ ヒガンバナは「葉見ず花見ず」の特性から、孤高の花とも言われます。
1本だけ咲く姿は「孤独」や「一途な想い」を象徴します。
2本のヒガンバナ
- 意味:決して交わらない関係、すれ違う恋
→ 2本並んでいても決して結ばれない存在を表し、「すれ違う愛」や「運命により引き裂かれた関係」を示します。
中国の「曼珠と沙華」の伝説(花と葉の妖精が出会えない悲恋)が由来として重なります。
3本のヒガンバナ
- 意味:死者への想い、供養
→ お彼岸の時期にお墓に3本供える風習もある地域があり、「亡き人を偲ぶ」意味合いが強い本数です。
5本のヒガンバナ
- 意味:情熱的な想い、深い縁
→ 赤いヒガンバナの「情熱」「独立」の花言葉と、奇数が縁起の良い数とされることから、「強い愛情や魂のつながり」を象徴します。
6本以上のヒガンバナ
- 意味:群生=魂の道案内、霊界への導き
→ ヒガンバナは群生して咲く習性があり、古くは「亡者の道を示す花」とされていました。
多く咲くことで「あの世への道を照らす花」と見なされ、死者供養の象徴的な意味が強まります。
本数による正式な花言葉は無し
- ヒガンバナは贈り物にはあまり用いられない花ですが、お墓や仏前に供える場合は奇数本(1本・3本・5本)が好まれる傾向があります。
- 本数による解釈は正式な花言葉ではなく、地域や文化によって異なります。
彼岸花の花言葉~海外ver

ヒガンバナ(彼岸花)は日本だけでなく、中国や韓国、欧米でも知られており、それぞれの地域で独自の花言葉や象徴的な意味を持ちます。海外では、仏教や民間伝承の影響、またその独特な生態や鮮烈な赤色から、死・別れ・再生・情熱といったイメージが共通して見られます。以下に国や地域ごとに詳しく紹介します。
海外①中国:曼珠沙華(まんじゅしゃげ)
花言葉・意味
- 「再会」「別れ」「輪廻転生」
- 「天上の花」「吉兆の印」
由来
- 仏教の経典に登場し、「曼珠沙華」は天界に咲く赤い花で、吉兆や聖なる出来事の前兆とされています。
- 一方、民間伝承では「黄泉の国(あの世)に咲く花」とされ、死者の魂を導く花としても語られます。
- また、「曼珠(花)と沙華(葉)」という二人の妖精が恋に落ちるも、神の掟により会えなくなり、花と葉が別々に存在するようになった悲恋の物語から、**「決して結ばれない愛」**の象徴ともされています。
海外②韓国:상사화(サンサファ / 相思華)
花言葉・意味
- 「あなたを想う花」「相思の花」「再会できない愛」
由来
- 韓国ではヒガンバナを「相思華(サンサファ)」と呼びます。「相思」とは互いに思い合うことを意味し、お互いを思いながらも会えない愛を象徴します。
- 花と葉が同時に存在しないことから「相思相愛だが会えない」という切ない意味が込められています。
- 恋愛や片思いの象徴として詩や歌にも登場する花です。
海外③欧米(英語圏など)
英語名
- Red Spider Lily(レッド・スパイダー・リリー)
- Hurricane Lily(ハリケーン・リリー)
- Cluster Amaryllis(クラスター・アマリリス)
花言葉・意味
- 「Death(死)」「Lost Memory(失われた記憶)」「Never to Meet Again(二度と会えない)」
- 一部では**「Passion(情熱)」**や「Rebirth(再生)」の意味もある
由来
- 欧米ではその鮮烈な赤色や墓地に咲くイメージから、死や別れの象徴とされます。
- また、台風(ハリケーン)の季節に咲くことから「Hurricane Lily」と呼ばれ、自然現象や儚さを象徴する花としても扱われます。
共通点と違い
- 共通点:日本・中国・韓国・欧米いずれも「死」「別れ」「再会できない愛」を象徴。
- 違い:
- 中国や仏教圏 → 死後の世界・輪廻転生・魂の導き
- 韓国 → 恋愛・相思相愛だが会えない愛
- 欧米 → 死や喪失・儚さ・悲しみ
ヒガンバナは世界中で「死や別れ」と結びつく一方、**「再生」「魂のつながり」「永遠の愛」**といったポジティブな意味も併せ持つ特別な花です。
彼岸花(ヒガンバナ)の面白いエピソード

- 曼珠沙華という名前の由来
サンスクリット語の「manjusaka」が語源で、「天上に咲く赤い花」という意味。仏典に登場する言葉です。 - 花と葉が同時に見られない理由
地下茎に養分を貯めており、効率的にエネルギーを使うために花と葉が時期を分けて生えるという特殊な進化を遂げました。 - 墓地に多い理由
昔は土葬が主流だったため、動物に掘り返されないよう毒のある彼岸花を周囲に植えて守ったといわれます。 - 地方ごとの呼び名
地域によっては「幽霊花」「地獄花」「雷花」など、さまざまな不思議な呼び方が残っています。
彼岸花と宗教的な背景

古くから仏教やお彼岸の行事とヒガンバナは深く結びついてきました。墓地や田んぼの畔に咲く赤い花は、あの世や故人を連想させることも多く、幽霊花・死人花といった呼び名もあります。しかし、その妖艶な赤色や独特な花びらの形状は多くの人々を惹きつける存在であり、花言葉の「情熱」や「追想」の意味とも重なります。
仏教における彼岸花の役割
彼岸花の学名は「Lycoris radiata(リコリス・ラジアータ)」で、ヒガンバナ科の多年草です。仏教ではサンスクリット語で「曼殊沙華(まんじゅしゃげ)」と呼ばれ、「天蓋花」として天上に咲く花とされています。曼殊は「赤色の花」、沙華は「花の名前」を意味し、吉兆や悟りの象徴としても知られています。日本に伝わったのは古く、平安時代以前に中国経由で伝来したと考えられています。
お彼岸と彼岸花の関係性
お彼岸の時期に彼岸花が見頃を迎えることから、彼岸花とお彼岸は密接に関係しています。秋の彼岸は故人を偲ぶ週間であり、この時期に墓地や周りに赤い花が咲く様子は、追想や再会の花言葉と結びつきます。人々は故人への思い出や供養の象徴として、彼岸花の存在を大切にしてきました。
彼岸花の毒性と注意点

彼岸花は美しい見た目に反して、球根に毒性があります。花屋勤務時代にもお客様から「毒があるって本当?」と質問を受けることが多くありました。
彼岸花の毒性について知るべきこと
ヒガンバナにはアルカロイド系の毒成分「リコリン」が含まれています。モグラやネズミを寄せ付けないため、古くは田畑や墓地に植えられてきました。毒性の理由から「死人花」「幽霊花」といった不吉な呼び名も生まれましたが、摂取しない限り危険は少なく、観賞用として楽しむ分には問題ありません。
安全に楽しむためのポイント
花を触るときは手袋を使い、切り花を扱う際は皮膚に触れた後に手を洗う習慣を持つと安心です。特に子どもやペットがいる家庭では、飾る場所に注意が必要です。毒性を理解した上で正しく扱えば、自宅でも美しい秋の花を安全に楽しめます。
彼岸花に関する言い伝えと文化

彼岸花には地域や文化に基づく多くの言い伝えがあります。
日本の彼岸花にまつわる昔話
日本では「彼岸花を持ち帰ると火事になる」という言い伝えが一部に残ります。これはヒガンバナが墓地に多く植えられたことから家庭に不吉なイメージを持ち込まないための教えでした。また、「あの世への道しるべ」という解釈もあり、赤い花びらが故人の魂を導くと考えられました。
彼岸花を使った作品・アートの紹介
アニメや文学作品でも、彼岸花は象徴的に描かれることが多いです。赤い花の妖艶な印象や「再会」「あきらめ」といった花言葉は、悲恋や追想のモチーフとして人気です。また、白色やピンク色の品種が使われる現代アートも増え、神秘的な雰囲気を演出する花材として活用されています。
彼岸花を贈る意味とシチュエーション

花屋の現場では「彼岸花をプレゼントにしても良いのか?」という質問を受けることがありました。
花束で贈る彼岸花の意味
一般的に、赤い花の情熱的な花言葉から恋愛の告白に用いられることも可能です。ただし、不吉なイメージや墓地の印象が強いため、贈る相手の感性や文化背景を考慮する必要があります。
特別な人へのプレゼントアイディア
白色やピンク色、黄色など希少な品種を用いたアレンジメントは、独特で印象的なプレゼントになります。花屋としては、リコリス属の花を他の秋の植物と組み合わせてブーケにすることで、神秘的で上品な雰囲気を演出できるとおすすめしていました。
彼岸花に関するよくある質問
彼岸花は本当に不吉なのか?
不吉という印象は、墓地や毒性に由来する文化的な背景によるものです。実際には花言葉に「情熱」「再会」「追想」といった前向きな意味もあり、誕生花として9月生まれを祝う花としても知られています。
彼岸花の誕生花としての魅力
赤色のヒガンバナは9月25日、白色は10月6日など、秋生まれの誕生花として登録されています。誕生花として贈る場合は、花言葉の「情熱」「思いやり」「再会」に重ねて、相手への温かい気持ちを伝えられます。
彼岸花と秋の風景
彼岸花は秋の風物詩としても親しまれています。
秋の風物詩を楽しむ方法
全国各地でヒガンバナの名所があり、見頃の時期には一面の赤い花が咲き誇る景色を楽しめます。埼玉の巾着田や奈良の明日香村は特に有名で、彼岸花が描く赤い絨毯は圧巻です。周りの秋の景色と調和し、追想や再会を感じさせる独特の雰囲気が漂います。写真やアニメ作品のモチーフとしても人気で、訪れるだけで秋の季節感を満喫できます。
彼岸花の他は?日本で人気の花々
日本で人気の高い花を、それぞれの良さを交えてご紹介します。
- 桜(サクラ)
日本の春を象徴する花で、短くも美しい花びらが一面に咲き誇る様子は、儚さと新しい始まりの象徴です。お花見文化をはじめ、人々の心に深く根付いています。 - 薔薇(バラ)
豊富な色と品種があり、愛や美の象徴として贈り物に最適。香りも魅力的で、エレガントな雰囲気を演出できることが人気の理由です。 - チューリップ
春の訪れを告げる花で、カラフルでかわいらしい形状が特徴。ガーデニングにも向いており、初心者からプロまで幅広く愛されています。 - 紫陽花(アジサイ)
梅雨時期に鮮やかな色彩で庭や公園を彩る花。花の色が土壌の酸性度で変わるため、育てる楽しみもあります。 - ひまわり
太陽のような大きな花が元気を与えてくれる夏の代表的な花。明るく陽気なイメージが子どもから大人まで幅広く支持されています。 - 菊(キク)
秋の風物詩で、長持ちすることから仏事や祭事にも使われます。繊細な花びらと豊かな香りが特徴です。 - コスモス
秋に風に揺れる様子が美しく、ピンクや白の花が優しい印象。野原や庭で自然な雰囲気を楽しめます。 - カーネーション
母の日の定番ギフトとして人気。長持ちし、様々な色があり、感謝や愛情を伝える花として喜ばれます。 - 梅(ウメ)
春先に咲く花で、香り高く、冬の寒さの中に咲く強さが日本人に愛されています。和の雰囲気を楽しむのに最適。 - 桔梗(キキョウ)
夏から秋にかけて咲き、涼しげな青紫の花が特徴。和風の庭や生け花に重宝される人気の花です。
これらの花は季節ごとに日本の自然や文化を彩り、多くの人々に親しまれています。
まとめ
彼岸花の花言葉は「情熱」「追想」「再会」「あきらめ」と多様であり、仏教やお彼岸、文化、毒性といった要素と深く結びついています。妖艶で神秘的な赤い花は、日本の秋を彩る存在として人々に愛され続けています。花屋の元店員としては、彼岸花の性質や花言葉を理解した上で、見頃の時期に観賞したり、希少品種を取り入れたプレゼントに活用するなど、安全で魅力的な楽しみ方をおすすめします。
ライター紹介 Writer introduction
Sato君
花屋で働いてた日本男児(O型) コピーライターの経験も活かし花に関して、わかりやすく&信ぴょう性がある記事作りを心掛けながら配信中。 instagramでは「動く!4コマ漫画~花言葉劇場」を投稿しています。