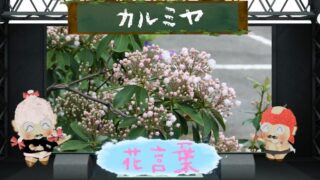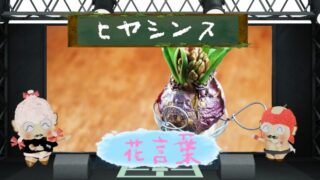コピーライターで花屋の元店員です。今回は秋の風物詩として人々の心を惹きつける「曼珠沙華(ヒガンバナ)」について、花言葉や文化的背景を中心に詳しく解説します。曼珠沙華の花言葉は「情熱」「再会」「あきらめ」など、多面的な意味を持ちます。
曼珠沙華(マンジュシャゲ)とは?基本情報

- 学名:Lycoris radiata
- 科・属:ヒガンバナ科 ヒガンバナ属
- 原産地:中国
- 開花期:9月中旬~10月上旬(秋のお彼岸の頃)
- 特徴:鮮やかな赤い花を放射状に咲かせ、葉は花後に伸びるため「葉見ず花見ず」とも呼ばれるユニークな植物。
良さ・魅力
- 季節感を強く感じられる花
秋のお彼岸の時期に一斉に咲くため、日本の原風景や秋の訪れを象徴する存在です。 - 群生の美しさ
田んぼのあぜ道や川辺に真っ赤な花が一面に広がる景観は圧巻で、観光名所にもなっています。 - 生命力の強さ
毒性を持つことから昔はモグラやネズミ除けに田んぼのあぜに植えられ、農作物を守る役割を果たしました。 - 日本文化との深い結びつき
万葉集や俳句にも詠まれ、秋の情緒や死生観と結びついた花として長く親しまれています。
曼珠沙華(マンジュシャゲ)の花言葉

曼珠沙華には複数の花言葉があり、その多くは「美しさ」と「別れ」の二面性を映しています。
代表的な花言葉
- 情熱
鮮やかな赤色が炎のように見えることから、燃えるような想いを象徴します。 - 再会
毎年、秋のお彼岸の頃に必ず姿を現すことから、「必ず巡り合う」という意味が込められています。 - あきらめ
葉と花が同時に出ない「葉見ず花見ず」の特性から、すれ違いや叶わぬ想いを示す花言葉とされました。 - 悲しい思い出
墓地やお彼岸と深く結びついてきた歴史から、死別や切ない別れを連想させる意味も含まれます。 - 独立
群生してもお互いが少し離れて咲く姿から、自立した強さを象徴するとされています。
花言葉が生まれた背景
- 日本文化との結びつき
墓地や田んぼのあぜに植えられてきたことから「死」「別れ」を連想させる花言葉が多いです。 - 植物の性質からの由来
葉と花が同時に見られないことが、「会いたくても会えない存在」を表す象徴になりました。 - 見た目の印象
真紅の花姿は燃える想いや情熱を表し、強い生命力を感じさせることからもポジティブな意味が与えられています。
ポジティブとネガティブの両面
- ポジティブ:「情熱」「再会」「独立」
- ネガティブ:「悲しい思い出」「あきらめ」
この二面性こそが、マンジュシャゲの花言葉の最大の魅力なんです。
曼珠沙華の花言葉~色別ver

曼珠沙華(彼岸花)は色によっても花言葉が異なります。それぞれの色合いが持つ印象や文化的背景から意味づけられているので、詳しくまとめますね。
赤い曼珠沙華(最も一般的)
- 代表的な花言葉:
- 「情熱」
- 「再会」
- 「あきらめ」
- 「悲しい思い出」
- 由来:
燃えるような赤は強い想いを表す一方、墓地やお彼岸と結びつき「別れ」の象徴ともなりました。
葉と花が出会わない性質から「すれ違い」「叶わぬ恋」を意味する言葉も生まれています。
白い曼珠沙華
- 代表的な花言葉:
- 「また会う日を楽しみに」
- 「思うはあなた一人」
- 由来:
白は清らかさや純粋さを表す色。赤に比べて柔らかく優しい印象を与えるため、再会への願いや純愛を意味する花言葉がつきました。
黄色い曼珠沙華
- 代表的な花言葉:
- 「深い思いやり」
- 「追想」
- 由来:
黄色は温かさや優しさを表す色。過去を大切に思い返す気持ちや、人を思いやる心を表す花言葉が与えられています。
ピンクの曼珠沙華(珍しい園芸品種)
- 代表的な花言葉:
- 「優しさ」
- 「恋の思い出」
- 由来:
赤の情熱と白の純粋さを合わせた色合いから、淡い恋心や柔らかい感情を象徴する言葉が生まれました。
色別まとめ
- 赤 → 情熱・再会・あきらめ
- 白 → また会う日を楽しみに・思うはあなた一人
- 黄 → 深い思いやり・追想
- ピンク → 優しさ・恋の思い出
赤は「強い想い」と「別れ」の両面性を持ち、白・黄・ピンクは比較的ポジティブで穏やかな意味が多いのが特徴です。
曼珠沙華の花言葉の由来は?

曼珠沙華(彼岸花)の花言葉は「情熱」「再会」といった前向きなものから、「悲しい思い出」「あきらめ」といった切ないものまで幅広くあります。その由来は大きく3つの要素に関係しています。
1. 植物の特徴からの由来
- 「あきらめ」「悲しい思い出」
曼珠沙華は「葉見ず花見ず」と呼ばれ、花と葉が同時に姿を見せません。花が咲く頃には葉はなく、葉が茂る頃には花が散るため「すれ違い」「決して結ばれない存在」とされ、切ない花言葉が生まれました。 - 「再会」
秋のお彼岸の頃に必ず咲きそろうことから、「必ず巡り会える」「約束の時に戻ってくる花」という意味が込められました。
2. 文化・歴史的背景からの由来
- 墓地や田んぼとの関わり
彼岸花は強い毒を持つため、昔は田んぼのあぜ道や墓地に植えられ、害虫や小動物を遠ざける役割を果たしていました。このため「死」「別れ」と結びつき、「悲しい思い出」「あきらめ」といった花言葉が定着しました。 - 彼岸と仏教との関係
お彼岸の時期に咲くことから、彼岸=あの世とのつながりを象徴する花として扱われ、別れや死者との縁を思い出させる意味合いが強まりました。
3. 名前(曼珠沙華)の由来
- サンスクリット語の「manjusaka」
仏典に出てくる言葉で「天界に咲く花」「吉兆を告げる花」という意味があります。
本来はとても縁起の良い名前ですが、日本に伝わる過程で墓地や死のイメージと結びつき、ポジティブとネガティブ両方の花言葉が生まれました。
由来まとめ
- ポジティブな由来:毎年必ず咲く → 「再会」/燃えるような赤色 → 「情熱」
- ネガティブな由来:花と葉がすれ違う → 「あきらめ」/墓や死との結びつき → 「悲しい思い出」
- 宗教的由来:「曼珠沙華」という名は仏教で「天上の花」を意味し、本来は吉兆の象徴
つまり曼珠沙華の花言葉は、「自然の性質」「人々の生活」「宗教的背景」が複雑に絡み合って生まれた、とても奥深いものなんです。
曼珠沙華の花言葉は怖いの?

曼珠沙華(彼岸花)の花言葉には「怖い」と感じられるものがありますが、それには理由があります。詳しく解説しますね。
怖いとされる花言葉
曼珠沙華には以下のような少し不気味な花言葉が伝わります。
- 「悲しい思い出」
- 「あきらめ」
- 「絶望」(一部の地域での解釈)
- 「また会う日を楽しみに」(裏を返せば、今は会えない=死別を連想する)
これらは「死」「別れ」「二度と会えない存在」といったテーマに直結するため、人々に「怖い花言葉」という印象を与えてきました。
なぜ怖い花言葉になったのか
- 墓や死と結びついた歴史
彼岸花は毒を持つため、昔から墓地や田んぼのあぜ道に植えられてきました。墓を守る花として身近だったことから、「死者」「あの世」と直結するイメージが強まりました。 - 花と葉が出会わない特性
「葉見ず花見ず」と呼ばれ、花と葉が同時に姿を見せません。
そこから「すれ違い」「会いたくても会えない」という切なさが「別れ」や「絶望」の象徴になりました。 - 地域ごとの異名
「死人花」「幽霊花」「地獄花」など、不吉さを感じさせる呼び名が日本各地にあります。これも「怖い花」というイメージを強めました。
でも実はポジティブな面もある
仏教由来の「曼珠沙華」という名は 「天界に咲く花」「吉兆の兆し」 を意味します。
また、毎年必ず彼岸に咲くことから「再会」「情熱」といった前向きな花言葉もあります。
つまり、曼珠沙華の花言葉は
- ネガティブな側面 → 死・別れ・絶望
- ポジティブな側面 → 再会・情熱・吉兆
両面をあわせ持つ、とても不思議で奥深い花言葉なんです。
まとめると、「怖い花言葉」があるのは事実ですが、それは死や別れに結びついた文化的背景が大きいんです。ただし同時に「吉兆の花」としての明るい意味も含まれています。
曼珠沙華の面白いエピソード

- 名前の由来:「曼珠沙華(まんじゅしゃげ)」はサンスクリット語の「manjusaka」から来ており、「天界に咲く赤い花」「吉兆を示す花」という意味があります。仏教由来で縁起の良い名を持ちながら、日本では墓地や彼岸と結びつけられるため「不吉な花」ともされる二面性を持ちます。
- 突然現れる花:葉と花が同時に見られないため、「いつの間にか真っ赤な花が咲いていた」という印象を強め、昔から不思議な花とされました。
- 地域ごとの呼び名:死人花、幽霊花、地獄花など少し怖い異名が多数存在し、民間信仰や伝承に深く関わっています。
- 海外での評価:欧米では「red spider lily」と呼ばれ、観賞用としても人気。日本ほど「不吉」とは思われず、エキゾチックな花として扱われています。
まとめると、マンジュシャゲは「美しいけれど不思議でちょっと怖い」独特の魅力を持つ花で、日本の秋を彩る象徴的な存在なんです。
曼珠沙華の文化的背景

曼珠沙華は単なる赤い花ではなく、日本文化や仏教思想と深く結びついた存在です。花びらの形、赤色の印象、開花時期などが人々に強い感情を呼び起こしてきました。
日本における歴史
日本における曼珠沙華(彼岸花)の歴史は古く、中国からリコリス属の球根植物として伝来したといわれています。田んぼのあぜ道や墓地に植えられた理由は、毒性を持つ鱗茎によってモグラやネズミから作物や遺体を守るためでした。このことから「死人花」「幽霊花」といった別名がつき、不吉なイメージと同時に、人々の生活を守る存在としての役割も担ってきました。
仏教との関連とその影響
曼珠沙華という名前はサンスクリット語の「マンジュシャカ」に由来し、「天蓋花(てんがいばな)」とも呼ばれます。仏教では吉兆を示す花として登場し、あの世とこの世をつなぐ象徴とされました。そのため、お彼岸の時期に咲く赤い花が故人を偲ぶ植物として広まりました。
言い伝えと迷信:幽霊花の神秘
曼珠沙華には多くの言い伝えや迷信が残されています。花と葉が同時に見られない「葉見ず花見ず」の性質から「再会できない」「あきらめ」といった花言葉が生まれました。また「地獄花」「幽霊花」という呼び名は、不吉な印象を強めています。しかし一方で「再会」「情熱」といった希望を込めた意味も持つため、人々の心に二重の感情を呼び起こす花といえます。
曼殊沙華の開花時期と見頃

曼珠沙華は開花時期が非常に特徴的であり、季節を象徴する植物として人気があります。花屋に勤めていた頃も、お客様から「今年はいつ頃見頃ですか?」とよく質問されました。
開花時期:9月中旬の意義
曼珠沙華は9月中旬から下旬にかけて開花します。ちょうど秋のお彼岸の時期に咲きそろうため「彼岸花」という名前が定着しました。この時期は昼と夜の長さが同じになる頃で、生と死を考える節目とされる点も、花の意味を深めています。
彼岸の時期との関係性
お彼岸は故人を供養する大切な週間です。墓地の周囲に咲く曼珠沙華は、まるで故人を迎え入れるかのような象徴的存在。赤い花びらの姿は、生者と死者の境界を彩る特別な印象を与えます。
人気のスポットと観賞方法
全国各地に曼珠沙華の名所があります。埼玉県日高市の巾着田曼珠沙華公園や、奈良県の明日香村の田園風景に咲く群生地は特に有名です。見頃の時期に訪れると、一面に広がる赤い花畑がまるで天蓋のように広がり、圧倒的な存在感を放ちます。観賞時は足元に注意しながら、写真撮影や静かに思い出を振り返る時間を楽しむのがおすすめです。
曼珠沙華の栽培と注意点

曼珠沙華は多年草であり、球根から育つ丈夫な植物です。ただし毒性を持つため、取り扱いには注意が必要です。
球根の育て方と管理方法
曼珠沙華はリコリス属に分類され、球根を植え付けて栽培します。日当たりの良い場所を好み、排水性の良い土壌で育てると元気に成長します。秋の開花後は葉が出て光合成を行い、鱗茎に栄養を蓄えます。植え付け後は数年間は植え替えをせず、自然のリズムを大切にすることがポイントです。
有毒性に関する注意点と対策
曼珠沙華の全般に毒性があり、特に鱗茎には強いアルカロイドが含まれています。誤って摂取すると嘔吐やけいれんなどを引き起こすため注意が必要です。花屋でも扱う際は「有毒植物なので小さなお子様やペットの近くには置かないでください」と説明していました。
様々な品種とその特性
赤色の曼珠沙華が最も有名ですが、シロバナマンジュシャゲやショウキズイセンなどの種類も存在します。白色の品種には「また会う日を楽しみに」、黄色の品種には「思いやり」など、色別の花言葉があります。最近ではピンク色の改良品種も登場し、より多彩な印象を楽しめるようになっています。
曼珠沙華にまつわる作品や文学

曼珠沙華は文学や芸術の題材としてもしばしば登場します。
題材にした有名作品
太宰治や与謝野晶子の作品に曼珠沙華は登場し、強烈な赤色や不吉なイメージを文学的に表現しています。また映画やドラマでも赤い花畑のシーンは象徴的に使われています。
作品に見るイメージ
作品の中で曼珠沙華は「情熱的でありながら哀しい存在」として描かれることが多いです。赤い花びらの様子は燃える炎のように見え、情熱を連想させる一方で、墓地や死者と結びつくため不吉さも表現されます。
文学における思い出と追想
曼珠沙華は文学作品の中で「思い出」や「追想」を象徴する存在です。過去の恋や失われた時間を回想する場面に登場し、読者に深い感情を呼び起こします。誕生花としての一面もあり、特定の日の思い出と重ね合わせて語られることもあります。
曼珠沙華の呼び名と地域差

曼珠沙華には多くの呼び名が存在し、地域ごとに特色があります。
ヒガンバナとマンジュシャゲの呼び方
「彼岸花」と「曼珠沙華」は同じ植物を指します。「彼岸花」は開花時期に由来し、「曼珠沙華」は仏教からきた名前です。それぞれの呼び方が花の持つ意味を異なる角度から伝えています。
地域ごとの特色と違い
地域によっては「死人花」「地獄花」など不吉な呼び名が伝わります。一方で「天蓋花」「陽気花」といった前向きな呼び方も存在し、人々の信仰や暮らしとの関わり方によって印象が変わってきました。
英語名・学名についての解説
曼珠沙華は英語で「Red spider lily」と呼ばれます。学名はLycoris radiataで、属名リコリスはギリシャ神話の海の女神に由来します。英語名の「lily(リリー)」は花びらの形からきていますが、分類上はヒガンバナ科に属する多年草です。
曼殊沙華の他は?日本で人気の花々
- チューリップ
春を代表する花で、色彩の豊かさが魅力です。赤や黄色、ピンクなど多彩な色合いが揃い、ガーデニングや花束に最適です。形もシンプルで可愛らしく、明るく元気な印象を与えてくれます。 - 薔薇(バラ)
「花の女王」と呼ばれるほど美しい姿と芳香が特徴です。愛や情熱を象徴し、贈り物や記念日に欠かせません。種類や品種が豊富で、豪華さから可憐さまで幅広い魅力を持ちます。 - 桜
日本を代表する花で、春の風物詩です。花の儚さと美しさが人々の心を惹きつけ、観賞だけでなく文化や詩歌にも多く登場します。お花見の楽しみも含め、人々の暮らしに寄り添っています。 - ひまわり
夏の象徴的な花で、太陽に向かって咲く姿が元気や希望を感じさせます。黄色の花びらが明るくエネルギッシュで、見る人に活力を与えてくれるのが魅力です。 - 梅
冬から春にかけて咲く早春の花で、寒さに耐えながら咲く強さと香りが魅力です。日本の伝統文化にも深く根付いており、気品と清らかさを象徴します。 - 菊
日本の国花の一つで、格式の高さと落ち着いた美しさがあります。品種によっては華やかさもあり、秋の風物詩として親しまれています。長寿や高貴さを連想させる点も魅力です。 - 紫陽花(あじさい)
梅雨の季節を彩る花で、土壌の酸性度によって色が変化する不思議さが特徴です。青や紫、ピンクの色合いが美しく、雨に濡れた姿は幻想的な雰囲気を持ちます。 - カーネーション
母の日の贈り物として定番の花です。赤は母の愛、ピンクは感謝など色ごとに花言葉が異なり、気持ちを込めやすいのが魅力です。可憐で日持ちが良い点も人気の理由です。 - コスモス
秋の代表的な花で、風に揺れる姿が可憐です。ピンクや白の花が一面に咲く景観は心を和ませ、親しみやすさと素朴な美しさが愛されています。 - 胡蝶蘭(こちょうらん)
優雅で豪華な花姿が特徴で、開店祝いやお祝い事に選ばれる定番です。花持ちが良く、蝶が舞うような花の形は幸せや繁栄を象徴します。
まとめ
曼珠沙華と花言葉には、歴史・文化・宗教・生活の知恵が深く結びついています。赤色の花は「情熱」「再会」「あきらめ」という二面性を持ち、白色や黄色などの品種は異なる意味を持ちます。墓地やお彼岸の象徴でありながら、文学や芸術では思い出や追想を呼び起こす存在でもあります。曼珠沙華が単なる不吉な植物ではなく、人々の暮らしを守り、故人を思う心を映し出す大切な存在であるということです。曼珠沙華を見かけた際には、その奥深い由来や花言葉を思い出し、秋の風景とともに味わっていければいいですね。
ライター紹介 Writer introduction
Sato君
花屋で働いてた日本男児(O型) コピーライターの経験も活かし花に関して、わかりやすく&信ぴょう性がある記事作りを心掛けながら配信中。 instagramでは「動く!4コマ漫画~花言葉劇場」を投稿しています。