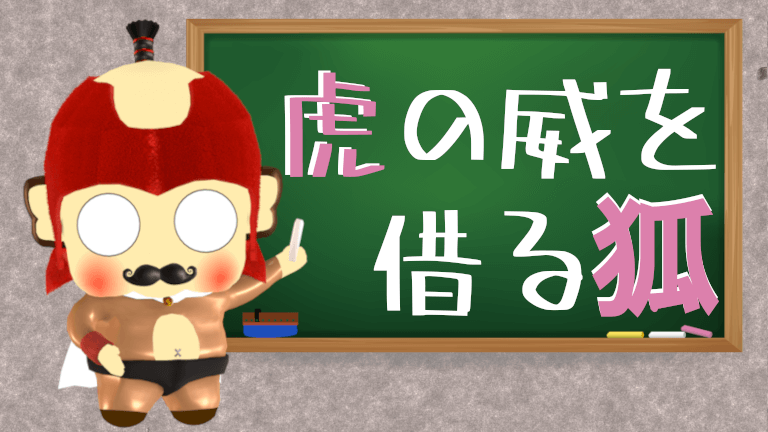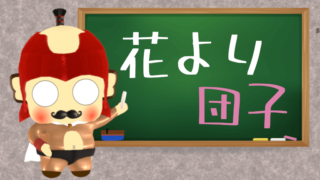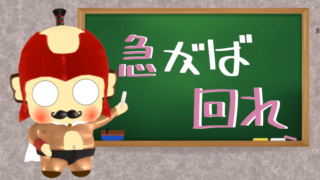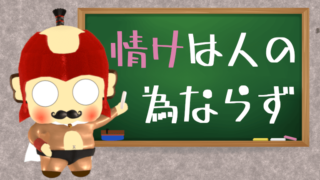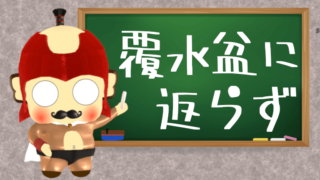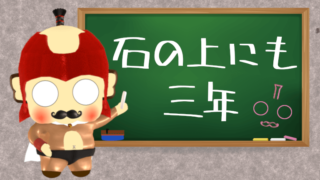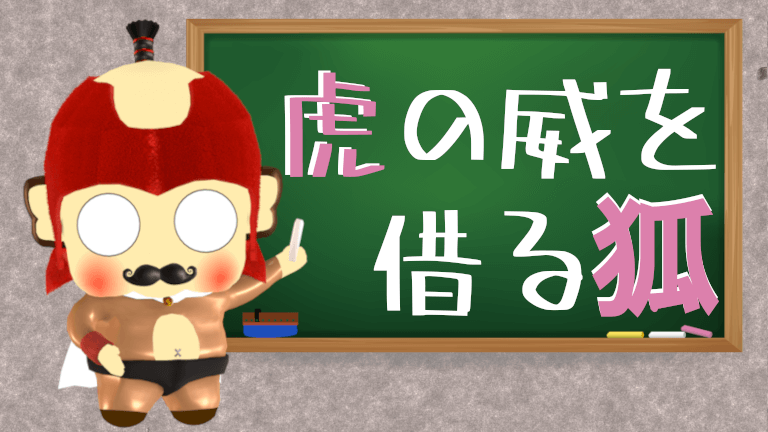
虎の威を借る狐の意味とは?

虎の威を借る狐には非凡な才能が見られる!
今回はこの故事成語の意味や現代語訳などをわかりやすく解説していきますね😊
虎の威を借る狐の意味~辞書編
広辞苑 第四版有力者の権威をかさに着ていばるつまらぬ者のたとえ。
権勢⇒権力・力
かさを着て⇒チカラに頼って
・本人自身は無力なくせに権力者の威光を借りて威張りくさる小心者のこと
・他人のチカラを頼りに、自分自身も強く見せかける弱者の意味
権力者と関係を持ち、弱者に対して自分にもチカラがあるんだぞと威張り、時に一緒にいじめたりする小心者の事を意味する故事成語。
ドラえもんで言えば、喧嘩の強いジャイアン(権力者)とつるんで、のび太(弱者)を一緒にいじめるスネ夫(小心者)のようなキャラと言えますかね?
どこの学校にも1人はいるだろう人物像と言えそうです。
どちらかというとネガティブな意味で使われることわざと言えるでしょう。
わかりやすく解説
「虎の威を借る狐」は、威勢のある力を持つ者や組織の力や権威を利用して、実際にはその力や地位を持たない者が自分の利益や地位を高めようとする様子を表現した言葉なのです。
わかりやすく解説すれば、次のような意味があります。
- 弱者が強者に頼る: 狐は本来、虎ほど強大な力を持っていませんが、その威勢を借りて自分を強く見せようとする行為を表現します。同様に、弱い立場にある人が、力や権威のある者に頼って自分の地位や利益を守ろうとすることを指します。
- 偽りの姿を装う: 狐が虎の皮を被るように、実際には弱い者が強者のような振る舞いをして自分を偽って見せようとすることを表現します。これによって、他人を欺いたり、自分の立場を利益を得るために装いを強化することがあります。
- 不正な手段を用いる: 虎の威を借る狐は、本来ならば手の届かない強大な力や地位を不正な手段で利用しようとすることもあります。これは、権力や地位を濫用する行為を指すこともあります。
この故事から、力や地位を持つ者が他者を支配したり自分の利益のために他者を利用する行為が批判されています。
また、この言葉は自分の立場を偽装して他人を欺こうとする行為なども意味しているんです。
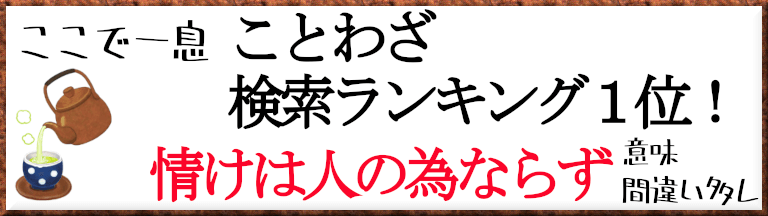
虎の威を借る狐の故事と由来
次は虎の威を借る狐の故事~主に民間や伝統的な文化の中で伝えられる物語や逸話のこと~から、この言葉の由来を紹介しますね。
戦国策の寓話
由来エピソードの戦国策の寓話。
戦国策⇒中国の書
寓話⇒人間の生活になじみ深い出来事を比喩によって表現し、それを通して教訓などを諭すための物語
ある日のこと、1匹の狐が猛獣である虎に食べられそうになった。
そんなピンチの状況で狐はある嘘を、虎に投げかけた。
狐:『私は天帝~天におられる最高の神~の使いである。私を食べれば天帝に背くことになろうぞ。うそだと思うなら私についてこい!』
疑わしく思った虎であったが、事実確認のため後ろをついていくと…なんと狐が歩く先に存在する獣たちは恐れながら逃げていくではないか!
そんな光景を見た虎は、狐が本当に天帝の使いだと信じてしまったのだった。
本当は後ろを歩く、虎の姿を見て獣たちは恐れて逃げているという真実を知らずに。
虎の威を借る狐の書き下し文と現代語訳
虎の威を借る狐は戦国策『借虎威』という原文(漢文)があります。
それも紹介しておきますが…
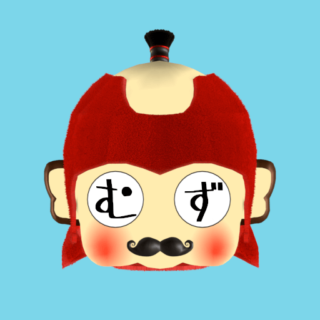
漢字が並んで目が痛いから興味ある人は見てみてね😅
書き下し文と現代語訳
書き下し文と現代語訳
漢文・書き下し文・現代語訳
虎百獣を求めて之を食らひ、狐を得たり。
虎が獣たちを探し求めては食べ、(あるとき)狐をつかまえた。
狐曰はく、子敢へて我を食らふこと無かれ。
狐が言うことには、あなたは決して私を食べてはいけません。
天帝我をして百獣に長たらしむ。
天帝が私を獣たちの王にならせたのです。
今子我を食らはば、是れ天帝の命に逆らふなり。
もしいまあなたが私を食べるならば、それは天帝の命令に背くことになります。
子我を以つて信ならずと為さば、吾子の為に先行せん。
あなたが私のことを本当でないと思うならば、私はあなたのために〔あなたの〕前に立って歩きましょう。
子我が後に随ひて観よ。
あなたは私のうしろについてきて、(その様子を)見なさい。
百獣の我を見て、敢へて走げざらんや。
あらゆる獣が私を見て、どうして逃げないことがありましょうか、いや、必ず逃げます。
虎以つて然りと為す。
虎は(狐の言うことを)もっともだと思った。
故に遂に之と行く。
そこでそのままこれ(狐)と一緒に歩いた。
獣之を見て皆走ぐ。
獣たちはこれ(狐といっしょに虎が歩いているの)を見てみな逃げた。
虎獣の己を畏れて走ぐるを知らざるなり。
虎は獣たちが自分をおそれて逃げたことに気がつかなかった。
以つて狐を畏ると為すなり。
(虎は獣が)狐をおそれているのだと思った。
虎の威を借る狐の例文集
「彼は、上司の名前を出して自分の提案を押し通そうとしているけれど、まるで虎の威を借る狐だね。自分の力では何もできないくせに。」
「その政治家は、有名な指導者の名前を借りて自らの政策を宣伝しているが、まるで虎の威を借る狐だ。自分の実績がないのに他人の名声にすがろうとするのはどうかしている。」
「あの会社は、大手企業のパートナーシップを強調して自社の価値を高めているが、実際には自らの実績やサービスの質が低くて問題がある。やっていることはまるで虎の威を借る狐のようだ。」
虎の威を借る狐の類語
続いては虎の威を借る狐の類語を紹介していきますね。
狐假虎威
<読み方>
不明
(こかこい)と推測される
虎の威を借る狐の中国成語バージョン。
この成語の読み方を調査してみましたが、確証的なモノが見つからず…。
ただ同じ意味を持つ『狐仮虎威(こかこい)』という四字熟語と1文字違いであり『假(か)』と読むから同じではないかと推測されていますよ。
権威を笠に着る
身近な例で言えば部活などで、むやみやたらにキレまくる顧問やコーチが該当するでしょう。
虎の威を借る狐との違いは、実際に権力のある人間が猛威を振るうという点ですね。
他人の威光で威張る
有名人または有名アーティストと1度しか会っておらず、ろくに話してもいないのに『あいつと俺は友達だぜ』と自慢げに話す酔っ払いの人が該当するでしょう😅
人の褌で相撲を取る
褌⇒ふんどし
他人から受けた支援や援助をもうやむやにし、自分の実力だけでヤッテきたという愚か者を表現する言葉でもあります。
その他の類語・単語
・尻馬に乗る
・親の七光り
虎の威を借る狐の対義語
虎の威を借る狐の対義語~反対の意味を持つ的確なことわざや言葉は見当たりませんでした。
似てるようでニュアンスが違うのは『猫を被る』自分の正体を明かさない表現や『能ある鷹は爪を隠す』など、本来はチカラがあるのに日常では見せびらかさず謙虚に過ごしているといったことわざが該当しますね。
虎の威を借る狐は別に虎に隠れておらず、むしろ存在を明かして威張っているという点が違っています。
虎の威を借る狐の英語表現
・A wolf sheep’s clothing
羊の皮を着た娘
・A fox that borrows the authority of a tiger.
虎の威を借る狐(直訳)
・Person who swaggers about under borrowed authority.
借りた権威の下でふんぞり返っている人物
虎の威を借る狐の日本語としての表現技法
虎の威を借る狐の日本語としての表現技法は、比喩やメタファーを用いた言い回しなのです。
具体的には、以下の要素が含まれています。
※メタファー:隠喩、暗喩とも呼ばれ、伝統的には修辞技法のひとつとされ、比喩の一種でありながら、比喩であることを明示する形式ではないものを指す。
1、比喩:虎の威を借る狐という表現は、狐が虎の力を借りて強さを装う様子を比喩している。
このような表現は、日常的な言語表現の中でもよく用いられており、一つの事象や状況を他の事物にたとえて描写することで、より強い印象を与える効果がある。
2、メタファー:虎の威を借る狐という表現は、狐と虎という具体的な動物を用いて、強い者の力を利用して自分を強く見せようとする人の行動を象徴的に表現している。このようなメタファーを使うことで、複雑な概念や抽象的なアイデアを具体的なイメージに置き換えて表現することができる。
以上のように、比喩やメタファーを用いた表現技法を通じて、『虎の威を借る狐』の意味や概念を明確に伝えることができるんです。
虎の威を借る狐の才能
上記の由来や書き下し文からもわかるように、虎の威を借る狐は口八丁~話し上手~という才能が見られます。
自分が喰われてしまいそうな状況で、これだけの作り話を仕立て上げ、九死に一生を得た狐にはトーク力に天賦の才能があったと言えるでしょう。
現実世界でも無口な人や口下手な人が権力者に擦り寄っていくのは難しく、反面アニメの世界ではスネ夫がジャイアンを良き気分にさせるトーク力で、連れ添いとして一緒に過ごすシーンが何度も見られます。
弱者が生き抜いていくために無意識のうちに身につけたチカラを表したことわざともいえるでしょう。
終礼
今回は虎の威を借る狐の意味や書き下し文などを解説させて貰いました。
世の中を生き抜いていくのに、狐のような知恵も必要になってくる時もあるでしょうけど、相手に不快感を与えるような使い方は避けたいところ。
強いものに頼るだけじゃなく、自分自身も力をつけて頼られる存在になりましょう!
ライター紹介 Writer introduction