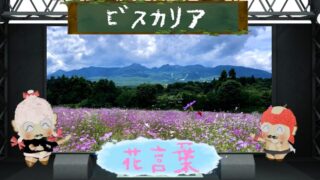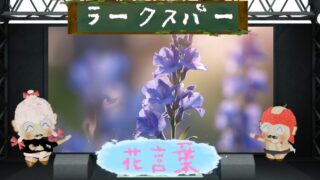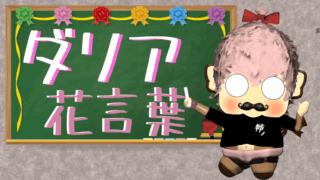コピーライターで花屋の元店員です。この記事では、独特な花姿と歴史を持つ「ヒオウギ(檜扇)」の花言葉について詳しくご紹介します。ヒオウギは古くから日本文化に根付き、花言葉の由来や誕生花としての意味、さらには栽培方法まで多面的に語られる植物です。その個性ある姿と花言葉は、贈り物や観賞用としても魅力を放ちます。
ヒオウギとは?基本情報

- 学名:Iris domestica(旧名:Belamcanda chinensis)
- 科属:アヤメ科ヒオウギ属
- 原産地:中国や日本を含む東アジア
- 開花期:7月〜8月
- 花の色:橙色に赤い斑点が入る鮮やかな花
- 名前の由来:葉の形が扇を広げた姿に似ていることから「檜扇」と名づけられました。
良さ
- 夏の庭を彩る花
真夏の暑さにも負けず鮮やかな橙色の花を咲かせるため、庭や花壇のアクセントとして人気です。 - 葉の美しさ
花だけでなく、扇を広げたような葉姿が端正で、和風庭園や茶花としても好まれます。 - 実の観賞価値
花後にできる黒い光沢のある種子は「ぬばたま(射干玉)」と呼ばれ、古くから和歌にも詠まれるほど風情があります。 - 育てやすさ
強健で乾燥や病害虫にも比較的強いため、初心者でも栽培しやすい植物です。
ヒオウギの花言葉

- 誠意
ヒオウギの扇のようにまっすぐ伸びる葉の姿から、真心を尽くす誠実さを表す花言葉がつけられました。飾り気がなく素直な心を表現する言葉です。 - 個性美
オレンジ色の花に赤い斑点が散りばめられた独特の模様は、他の花にはない個性的な魅力を持ちます。そのユニークさが「個性美」という花言葉につながっています。 - 誠実な心
古くから和歌や祇園祭など文化に結びつき、清らかでまじめな印象を与えることから「誠実さ」も象徴します。信頼や真心を込めて贈るのにふさわしい花言葉です。 - 強い心
真夏の暑さの中でも力強く咲く花の姿から、「困難に耐える心」「逆境に打ち勝つ強さ」をイメージして付けられています。
花言葉が生まれた背景
- 葉の形と名の由来
扇の形をした葉がまっすぐ広がる姿が「誠実さ」「真心」を連想させました。 - 鮮やかな花色と模様
オレンジに斑点模様という特徴的な花の姿が「個性美」と結びつきました。 - 古典文化との関わり
祇園祭や万葉集で親しまれ、長い歴史の中で「清らかさ」「誠意」といった意味が重ねられてきました。
ヒオウギの花言葉は「誠意」「誠実」「個性美」「強い心」といった前向きで力強い意味が中心で、贈り物としても縁起の良い花とされています。
ヒオウギの色別 花言葉

一般的にはオレンジ色に赤い斑点の入った花の多いヒオウギ(檜扇)ですが、園芸品種や変種には黄色や紅色なども見られ、それぞれに結び付けられた花言葉があります。
オレンジ色のヒオウギ
- 花言葉:「個性美」「誠意」「強い心」
- 意味:最も代表的な花色で、夏の太陽のように明るく力強い印象があります。赤い斑点の模様が独自性を感じさせ、「他にない魅力」「自分らしさを大切にする心」としての花言葉につながっています。
黄色のヒオウギ(園芸品種)
- 花言葉:「純粋」「素直な心」
- 意味:黄色い花は清らかで明るいイメージがあり、真心や素直な思いを象徴します。相手に誠意を伝える贈り物としてふさわしい色です。
赤色・紅色のヒオウギ
- 花言葉:「情熱」「決意」「勇気」
- 意味:赤い花は炎を思わせる力強さを持ちます。困難に立ち向かう姿や、揺るぎない決意を表し、勇気づけたい相手に贈るのに適しています。
黒い実(ぬばたま)
- 花言葉:「誠実」「永遠」「神秘」
- 意味:花が終わったあとにできる黒く光沢のある実は「ぬばたま」と呼ばれ、古来より夜や闇の枕詞として和歌に詠まれました。そこから「永遠」「奥深い美」「神秘」といった意味が重ねられています。
色別まとめ
- オレンジ:個性美・誠意・強い心
- 黄色:純粋・素直な心
- 赤色:情熱・決意・勇気
- 黒い実:誠実・永遠・神秘
ヒオウギは、花そのものだけでなく実にまで花言葉が与えられている珍しい植物です。
贈る色や実の意味を知って使い分けると、より深い思いを込められます。
ヒオウギの花言葉の由来

ヒオウギ(檜扇)の花言葉には「誠意」「誠実」「個性美」「強い心」などがありますが、これらには古典文化や花の形・性質に由来があります。
1. 「誠意」「誠実」
- 由来:ヒオウギの葉は、まるで扇を広げたように左右にまっすぐ伸びます。その端正で清らかな姿が「素直さ」「誠実さ」を象徴するとされました。
- 文化的背景:祇園祭では「檜扇飾り」にヒオウギが用いられ、厄除けや誠実な祈りの象徴とされたことも由来の一つです。
2. 「個性美」
- 由来:ヒオウギの花は、オレンジの花弁に赤い斑点が散る独特の模様をしています。他の花にはないその個性的な美しさから「個性美」という花言葉が生まれました。
- ポイント:整った美ではなく「自分らしさの中にある美」を讃える意味合いがあります。
3. 「強い心」
- 由来:ヒオウギは真夏の炎天下でも元気に咲き、乾燥や暑さにも強い植物です。その生命力が「困難に耐える心」「逆境に打ち勝つ強さ」に重ねられました。
- エピソード:古来から薬用植物としても利用され、喉の炎症を鎮めるなど人々を助けてきたことも、強さのイメージに関わっています。
4. 「神秘」「永遠」(黒い実=ぬばたま)
- 由来:花が終わった後にできる黒く光沢のある種子は「ぬばたま」と呼ばれ、万葉集などの和歌で「夜」「闇」「黒髪」などを導く枕詞として使われました。
- 意味:この「ぬばたま」が夜や闇、永遠を連想させ、そこから「神秘」「誠実」「永遠」といった花言葉が生まれています。
由来まとめ
- 葉の形 → 誠意・誠実
- 花の模様 → 個性美
- 夏に強い性質 → 強い心
- 黒い実(ぬばたま) → 神秘・永遠
ヒオウギの花言葉は、自然の姿や性質と、日本の伝統文化(祇園祭・和歌・薬用利用)が深く結びついて生まれたものです。
とても「日本的」な背景を持つ花言葉と言えますね。
ヒオウギの花言葉は怖いの?

ヒオウギ(檜扇)の花言葉は基本的にポジティブな意味が多く、「怖い」ものではありません。ただし、花の後にできる黒くつややかな種子「ぬばたま」に関わる表現が、やや「不気味」「神秘的」に感じられることがあるため、「怖いの?」と思われることがあるようです。
「怖い」と言われる背景
- 黒い種子「ぬばたま」
ヒオウギの実は黒く光沢があり、古代から「ぬばたま」と呼ばれました。和歌では「ぬばたまの夜」「ぬばたまの黒髪」といった枕詞として使われ、夜・闇・死などと結びつけられることが多かったため、「少し不気味」なイメージを持たれたことがあります。 - 闇との結びつき
闇や夜は古代の人々にとって「未知」や「恐れ」の象徴でした。そのため「ぬばたま」という言葉から、怖さを連想してしまう人もいます。 - 祭礼との関係
祇園祭などで邪気を祓う植物として飾られることもあり、魔除け的な側面が「畏れ」と結びついたとも言えます。
実際の印象
- 花そのものの花言葉(誠意・個性美・強い心)は、むしろ前向きで人を励ますもの。
- 実にまつわる「ぬばたま」から、闇や死を連想する人がいて「怖い」と言われることもあるが、これは神秘的な魅力の裏返しとも言えます。
怖いよりも力強い
ヒオウギの花言葉自体は「怖いもの」ではなく、むしろ力強さや誠実さを表す縁起の良い意味が中心です。ただし「ぬばたま(黒い実)」が古典文学で夜や闇に結びついたために、一部で「怖い」と連想されることがある、という背景があるのです。
ヒオウギの面白いエピソード

- 和歌や万葉集に登場
黒くつややかな種子は「ぬばたま」と呼ばれ、「ぬばたまの夜」「ぬばたまの黒髪」など、夜や闇の枕詞として万葉集や古典文学に多く使われています。 - 京都・祇園祭との関わり
ヒオウギは祇園祭の際、無病息災を祈って飾られる「檜扇」飾りに使われることがあります。古くから邪気を払う植物と信じられてきました。 - 薬用としての利用
根茎は「射干(やかん)」と呼ばれ、漢方薬として咳や喉の炎症に効能があると伝えられています。
夏の鮮烈な花色と古典文化に深く関わる歴史を持ち、見た目の美しさだけでなく文化的背景や薬用的価値まで備えた奥深い植物です。
ヒオウギの実と毒性について
ヒオウギは花だけでなく、独特の黒い種子「ぬばたま」も注目を集める植物です。その美しさは和歌にも詠まれ、文化的価値が高い一方で、毒性についても注意が必要です。ここではヒオウギの実と安全性に関する知識を整理します。
ヒオウギの実とは何か
ヒオウギの実は、花が終わったあとに房の中で熟す黒い光沢をもった種子です。この種子は「ぬばたま」と呼ばれ、古代から装飾や詩歌の題材として愛されてきました。夜や闇を象徴する言葉として万葉集などに登場し、日本人の美意識に深く結びついています。花屋でも、ドライフラワーやアレンジメントの素材として人気があります。
ヒオウギの毒性と安全性
ヒオウギの種子や根にはわずかな毒性があるとされます。ただし、強い毒ではなく、観賞用として触れる程度で人体に危険を及ぼすことはほとんどありません。しかし誤食すれば下痢や腹痛を引き起こす可能性があるため、小さなお子様やペットがいる家庭では注意が必要です。
毒性に関する注意点と安全な扱い方
扱い方としては、観賞や飾りとして楽しむ分には全く問題ありません。万一、誤って口に入れてしまうと体調不良の原因になるので、食用と誤解しないことが大切です。花屋で勤務していたときも、お客様に「観賞専用です」と必ずご案内していました。誠意を持って安全性を伝えることで、安心して楽しんでいただけます。
ヒオウギと文化

ヒオウギは日本の伝統行事や文化に深く結びついており、その名前や形に象徴性が込められています。
祇園祭の関係
京都の祇園祭では、ヒオウギが邪気を払う植物として使われてきました。檜扇のように広がる葉の形は、扇を広げるようで縁起が良いとされ、祭礼や飾りに重宝されました。花屋としても、祇園祭の季節にはヒオウギを求めるお客様が多く、文化的な需要を強く感じたものです。
別名とその意味
ヒオウギは学名をIris domesticaといい、英語では“Leopard flower”と呼ばれます。花びらに散る斑点模様がヒョウ柄を思わせることが由来です。日本名の「檜扇」は、葉の形が檜の板で作られた扇に似ていることから生まれました。こうした名前の由来は、その植物の個性や文化的背景を理解する手がかりになります。
日本文化におけるヒオウギの位置づけ
ヒオウギは和歌や俳句に詠まれ、文学的なモチーフとしても重要です。黒い種子「ぬばたま」は夜の比喩として使われ、「ぬばたまの夜」といった表現が広く知られています。日本文化におけるヒオウギの位置づけは、単なる観賞植物を超えた象徴的な存在といえるでしょう。
ヒオウギの誕生花としての意義
花言葉と同様に、誕生花の概念は贈り物や人との結びつきを深めるものです。ヒオウギが誕生花として選ばれる背景には、強い個性と文化的価値があります。
誕生花とその意味
ヒオウギは8月の誕生花として知られています。花言葉には「誠意」「個性」「誠実な心」といった意味が込められています。これらは、扇を広げるように伸びやかに咲く花姿や、他の花にない模様から導かれたものです。花屋の経験からも、夏の贈り物に選ばれることが多く、強い印象を残す花だと感じます。
ヒオウギを贈る際のポイント
ヒオウギを贈るときには、花言葉を添えると気持ちが伝わりやすくなります。誠意や個性を象徴する花として、特に大切な人へのギフトに適しています。花束に他の夏の花を組み合わせることで、鮮やかで華やかな印象を作ることができます。
お印としてのヒオウギの活用法
ヒオウギの葉や実は、古くから「お印」としても活用されてきました。祭礼や行事で飾られるだけでなく、現代でも茶花やアレンジメントに使われます。独自の形と色彩が、他の花にはない存在感を与えます。
ヒオウギを育てるための基礎知識

ヒオウギは観賞用としても育てやすい植物です。丈夫で強い生命力を持ち、ガーデニング初心者にもおすすめできます。
ヒオウギの栽培に関する情報
ヒオウギは多年草で、地下に根茎を持ちます。春に植え付けを行えば、夏には花を咲かせます。種子から育てることも可能ですが、根茎での増殖が一般的です。学名に示される通り、園芸植物として広く親しまれています。
適した環境と育て方
日当たりと水はけの良い環境を好みます。乾燥に強いので、過湿を避ければ元気に育ちます。花屋で販売するときも「手間がかからず初心者向き」と説明していました。鉢植えでも庭植えでも楽しめる点が魅力です。
ヒオウギの花を長持ちさせる方法
切り花として楽しむ場合は、水替えをこまめに行うことが重要です。さらに涼しい場所に置くことで、鮮やかな花を長持ちさせられます。花びらの模様が散り始めても、種子が観賞価値を保ち、長く楽しむことができます。
関連する花言葉や植物の紹介

ヒオウギに関連する植物や花言葉も多く存在します。比較することで、その個性や由来がより深く理解できます。
他の花の意義とヒオウギとの違い
例えば、薔薇の花言葉は「愛」、桜は「儚さ」を象徴します。それに対し、ヒオウギは「誠意」や「個性」といった人間性を表現します。花言葉の違いから、それぞれの花が持つ役割や贈り方の意味を考えることができます。
ぬばたまやシャガの花言葉
ヒオウギの種子「ぬばたま」もまた、夜や闇を象徴する言葉として文学に登場します。また、同じアヤメ科のシャガは「友人が多い」という花言葉を持ち、社交性を象徴します。同じ科の植物でも、与えられる意味や文化的背景は異なります。
ヒオウギの仲間たち
ヒオウギには近縁種があり、園芸品種も存在します。交配により生まれた花々は色彩や模様が豊かで、観賞用として人気があります。これらの仲間と比較することで、檜扇という名前を持つ植物の個性がより際立ちます。
ヒオウギの他は?日本で人気の花々
- チューリップ
春を代表する花で、色とりどりのバリエーションが魅力です。赤・黄・ピンクなど彩り豊かで、ガーデニングや花束に最適。花言葉も「思いやり」や「博愛」など前向きで贈り物にも喜ばれます。 - 薔薇
気品と豪華さを兼ね備えた永遠の人気花。愛や美を象徴し、誕生日や記念日には欠かせない存在です。品種や色によって花言葉が変わり、深いメッセージを込められるのも大きな魅力です。 - 桜
日本の春を象徴する国花的存在。花見文化にも根付いており、人々を集めて心を和ませます。儚さと美しさを併せ持ち、人生や季節の移ろいを感じさせる点が特別です。 - ひまわり
夏の太陽を思わせる元気な花。大輪の花が明るい雰囲気を演出し、前向きな気持ちを与えてくれます。花言葉は「憧れ」や「情熱」で、プレゼントにもぴったりです。 - カーネーション
母の日の定番花で、感謝や愛情を表すシンボル。赤・ピンク・白など多彩な色があり、花もちも良いためアレンジメントや贈答用に最適です。 - ユリ
上品で香り高い花。純白のカサブランカをはじめ豪華さが際立ちます。花束や式典、祭事などフォーマルな場にふさわしい優雅さが魅力です。 - アジサイ
梅雨の風物詩で、青や紫、ピンクに変化する花色が美しい植物。土壌の酸度で色が変わる不思議さも魅力で、庭植えや鉢植えで人気があります。 - コスモス
秋の花として親しまれ、風に揺れる可憐さが魅力。群生すると一面の花畑となり、観光地としても人気です。花言葉は「調和」「謙虚」で、季節を彩るやさしさを持ちます。 - 梅
早春を告げる香り高い花。桜よりも先に咲き、寒さの中で凛とした美しさを見せます。花言葉は「高潔」「忍耐」で、日本文化に古くから親しまれてきました。 - 菊
日本を代表する伝統花で、皇室の象徴としても知られています。長寿や高貴の意味を持ち、秋を代表する花。仏花としてだけでなく、洋風アレンジでも華やかに映えます。
まとめ
ヒオウギは、その個性的な花姿と文化的背景から、日本で長く愛されてきた植物です。花言葉には「誠意」「個性」が込められ、贈り物や誕生花として強い印象を与えます。祇園祭など文化行事との結びつきも深く、誇りある日本の花といえるでしょう。扱いやすく魅力的な植物だと実感します。ヒオウギの魅力を知り、花言葉の由来に触れることで、より豊かな花の楽しみ方が広がります。
ライター紹介 Writer introduction
Sato君
花屋で働いてた日本男児(O型) コピーライターの経験も活かし花に関して、わかりやすく&信ぴょう性がある記事作りを心掛けながら配信中。 instagramでは「動く!4コマ漫画~花言葉劇場」を投稿しています。