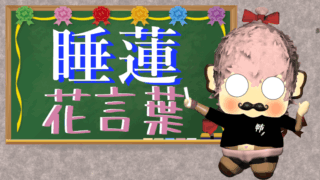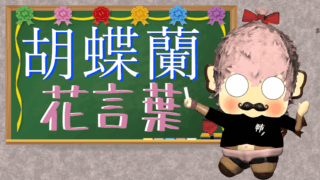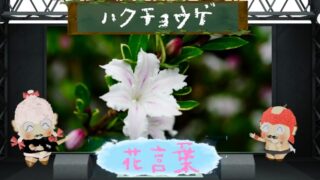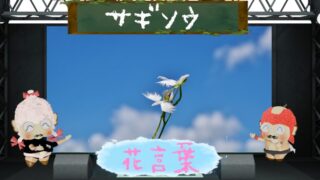コピーライターで花屋の元店員です。今回は、ホオズキ(鬼灯)の花言葉とその魅力、季節や育て方、ギフトとしての使い方まで詳しくご紹介します。鮮やかなオレンジ色の果実を包むガクは、夏の風物詩として多くの人に愛されています。
ホオズキとは?基本情報

- 和名:ホオズキ(鬼灯、酸漿)
- 学名:Physalis alkekengi var. franchetii
- 科・属:ナス科ホオズキ属
- 原産地:東アジア(日本、中国など)
- 形態:多年草(観賞用は一年草扱いが多い)
- 開花期:6〜7月(白〜淡黄色の小花)
- 実(萼)の色づき:7〜8月頃に萼が膨らみ、赤く熟す
- 特徴:花が終わったあと、萼が袋状に膨らみ、赤く色づく。この袋が“提灯”のような形で、中には赤い実が入っている。
良さ・魅力
- 独特の美しい姿
袋状の萼が鮮やかな朱色に染まり、夏の風物詩として涼しげな印象を与える。切り花やドライフラワーにも人気。 - お盆との関わり
日本では「鬼灯」の名で、お盆の供え物に用いられる。先祖の霊を迎える提灯の意味を持つ。 - 観賞と薬用の両面
古くは実や根が漢方薬として咳止め・解熱などに利用された(ただし未熟な実や根は毒性があり注意)。 - ドライにして長持ち
萼は乾燥させても形や色を比較的保つため、インテリアとして楽しめる。 - 種の透かし細工
萼だけを網目状に残す“ほおずき透かし”は、美しい工芸的飾りになる。
ホオズキの花言葉

ホオズキ(鬼灯)の全般的な花言葉について、ひとつひとつの意味と由来を掘り下げて説明します。
全般的な花言葉
- 偽り
- 意味:外見は立派だが中身はそうでもない、というニュアンス。
- 由来:ホオズキは大きく膨らんだ赤い袋状の萼の中に、小さな果実が入っています。この“見た目の華やかさ”と“中身のギャップ”が「偽り」という意味に結びつきました。
- ごまかし
- 意味:事実を隠したり、体裁を整えること。
- 由来:「偽り」と同様に、外側の袋が実を覆って中が見えないことから、何かを隠しているイメージにつながります。
- 欺瞞(ぎまん)
- 意味:人をあざむくこと、真実を覆い隠すこと。
- 由来:ホオズキの中空な構造や、実が見えないことからの派生。英語の花言葉 Deception(欺き)にも相当します。
- 自然美
- 意味:自然の中で見せる美しさ、人工的でない魅力。
- 由来:鮮やかな朱色と独特の形が、夏の緑と対比して非常に映えることから。特にお盆の飾りとして日本的な美意識に合致します。
- 心の平安
- 意味:落ち着き、安らぎ、心の静けさ。
- 由来:お盆にホオズキを飾る習慣が、先祖を迎え心を落ち着ける時間と結びつき、このようなポジティブな花言葉も生まれました。
- 不思議
- 意味:神秘的、普通ではない魅力。
- 由来:萼が風船のように膨らみ、中に実を包み込むという珍しい構造が、見る人に神秘的な印象を与えるためです。
面白いのは、ホオズキの花言葉は**「偽り」や「欺瞞」といったネガティブ系と、「自然美」「心の平安」といったポジティブ系**の両方が存在していることです。
これは、ホオズキが持つ二面性(中身を隠す袋と、美しい見た目)をそのまま反映しています。
ホオズキの花言葉~色別ver

ホオズキ(鬼灯)の色別の花言葉について詳しくまとめます。
ホオズキは基本的に赤橙色ですが、観賞用改良種や染色加工によって白・黄色・金色などのバリエーションも見られます。
色別花言葉
1. 赤・橙色(もっとも一般的)
- 花言葉:「偽り」「ごまかし」「欺瞞」
- 意味と由来:
外側の朱色の袋(萼)がふっくらとしているため、中に大きな実があるように見えますが、実は小さく中空に近い構造。このギャップから「偽り」や「ごまかし」といった花言葉が生まれました。
一方で、日本ではお盆の提灯に見立てられ、故人を偲ぶ飾りとして「心の平安」という意味も持ちます。
2. 白色(改良種や染色加工品)
- 花言葉:「清純」「平和」
- 意味と由来:
白は清らかさや穢れのない心を象徴する色。お盆や供養の飾りとして使われる場合、故人の魂を清らかに迎え送るという意味も込められます。
改良品種として白い袋のホオズキは稀少で、特別感があります。
3. 黄色(園芸改良や染色品)
- 花言葉:「富」「繁栄」
- 意味と由来:
黄金色に輝く袋の姿から、豊かさや実りを象徴。特に正月飾りや縁起物として使われることもあります。
4. 金色(正月飾りや工芸品)
- 花言葉:「財運」「幸運」
- 意味と由来:
金色は古来より財や福を呼び込む色とされ、商売繁盛や家運隆盛の縁起物として重宝されます。染色されたドライホオズキや金箔加工品が有名です。
5. 透かしホオズキ(色より形が特徴)
- 花言葉:「儚い美」「愛の保護」
- 意味と由来:
萼の部分を水や虫により自然に溶かし、網目状だけ残した姿。中の実が透けて見える様子は、美しさと同時に壊れやすさを感じさせ、「儚さ」の象徴となります。
フランスでは「Amour en cage(檻の中の愛)」と呼ばれ、愛を守る象徴として扱われます。
ホオズキの花言葉は怖いの?

ホオズキ(鬼灯)の花言葉は、確かに少し“怖い”と感じられるものがあります。
特に「偽り」「ごまかし」「欺瞞」などのネガティブ系花言葉は、その背景や由来を知ると少しぞっとするような意味合いを持っています。
なぜ怖い花言葉が付いたのか
- 見た目と中身のギャップ
ホオズキは袋状の朱色の萼が大きく膨らんでいますが、中にある実は意外と小さく、中空に近い構造です。
この「外側は立派でも中身はそうでもない」という点が、人を欺く・騙すイメージに結びつき、「偽り」「欺瞞」という言葉になりました。
→ 人間関係にも当てはめられるため、贈り物としては意味を誤解されることがあります。 - お盆との関わりによる“霊的”イメージ
日本ではお盆に「鬼灯(提灯)」として先祖の霊を迎える飾りに使われます。
「鬼」という字や、死者の世界と現世をつなぐ役割から、“あの世の灯り”として少し不気味に感じる人もいます。 - 毒性の存在
観賞用ホオズキは未熟な実や根にソラニンなどの毒成分を含むため、食べると危険。こうした“毒を持つ美しい植物”は昔から警戒や畏怖の対象でした。
怖いだけじゃない面
- ホオズキの花言葉には、ネガティブなものだけでなく「自然美」「心の平安」「不思議」といった美しい意味もあります。
- お盆の灯りとしては“霊を導く優しい光”の象徴でもあり、怖さよりも厳かさや温かさを感じる文化もあります。
- 海外ではフランス語で「Amour en cage(檻の中の愛)」と呼ばれ、むしろロマンチックな意味合いが強いです。
つまり、ホオズキの花言葉が怖いとされるのは、見た目と中身のギャップ+死者の世界との結びつきが原因です。
ですが、その背景を知ると、単なる恐怖ではなく、人間の生死観や美意識が込められた深い象徴だということがわかります。
ホオズキの面白いエピソード・豆知識

- 浅草の「ほおずき市」
毎年7月9日・10日、浅草寺で開かれる「四万六千日」とともにほおずき市が開催され、縁日気分で色鮮やかなホオズキが並ぶ。「四万六千日」は、この日に参拝すると46,000日参拝したのと同じご利益があるといわれる日。 - “鳴らす”遊び
実を食べたあと、皮を破らずに種を取り除き、口に含んで音を出す「ほおずき鳴らし」は、昔の子どもの遊びの一つ。特に女の子の夏の遊びとして親しまれた。 - 名前の由来
「ホオズキ」は、赤く色づく袋を「頬が赤くなる」様子になぞらえた説や、「ホオ(頬)」+「スキ(透き)」から来た説がある。 - 食用ホオズキとの違い
観賞用ホオズキは苦味や毒性があり食用には向かないが、近縁種の「ストロベリートマト(食用ほおずき)」は甘酸っぱくて食べられる。
ホオズキの誕生花と季節
ホオズキは7月〜8月にかけて旬を迎える多年草で、日本の夏の風景に欠かせない存在です。誕生花としての登録は7月9日・7月10日・8月12日などがあり、特にお盆の時期と深い関わりを持ちます。
花屋時代、お盆前になると「ほおずき市」で購入された鉢植えや切り枝を持ち帰るお客様が増えました。赤やオレンジの袋状の萼(ガク)が提灯のように揺れる姿は、まさに夏の象徴です。
ホオズキが誕生花として選ばれる理由
ホオズキの誕生花としての意味には、「偽り」「ごまかし」などの花言葉もありますが、「自然美」「心の平安」という温かい意味も含まれています。これはお盆の飾りとして、祖先を迎える灯りに見立てられた歴史からきています。誕生日に贈る場合は、ネガティブな意味を避け、自然美や安らぎの象徴として伝えるのが花屋のコツです。
ホオズキの開花時期と育て方
開花は6月〜7月。小さなクリーム色や白い花が咲いた後、萼が膨らみ鮮やかなオレンジ色に変化します。栽培は日当たりと水はけの良い土が必要で、ナス科植物のため連作障害に注意しましょう。成長期には追肥と十分な水やりがポイントです。
誕生日プレゼントとしてのホオズキ
花屋での経験では、誕生日プレゼントにホオズキを選ぶ方は珍しいですが、和風スタイルのフラワーアレンジや鉢植えとして贈ると印象的です。特にガーデニング好きや季節感を重んじる方へのギフトにおすすめです。
ホオズキの種類と特徴

ホオズキの和名は「酸漿(かんしょう)」で、学名は Physalis alkekengi var. franchetii。英名は “Chinese lantern” や “Japanese lantern”。原産地は東アジアです。
イヌホオズキとその花言葉
イヌホオズキは野生に自生するナス科植物で、見た目は似ていますが果実は黒く、花も小さく目立ちません。花言葉は「真実」や「信頼」で、ホオズキとは対照的です。
ホオズキの品種と使い方
観賞用はオレンジ色が定番ですが、黄色や白の改良品種もあります。切り花、鉢植え、ドライフラワー、透かしホオズキなど多様な楽しみ方があります。
ホオズキの人気と魅力
夏の風物詩としての存在感、提灯のような特徴的な見た目、そしてお盆やほおずき市といったイベント性が人気の理由です。
ホオズキの歴史と文化

平安時代のホオズキの位置づけ
平安時代には薬草として利用され、「酸漿水」が解熱や咳止めに用いられました。和歌や物語にも登場し、自然美の象徴とされました。
鬼灯(ホオズキ)の言い伝え
鬼灯はお盆に霊を導く灯りとされ、「あの世とこの世をつなぐ植物」として信仰されました。
ホオズキにまつわる伝説と俗信
「袋を破ると運が逃げる」「透かしホオズキを持つと恋が成就する」などの俗信も残っています。
ホオズキをギフトにする方法

ホオズキの観賞とイベント
室内観賞では涼しげな和風インテリアとして映えます。ドライ加工で長期間楽しめます。
ホオズキ市とその楽しみ方
浅草寺の「ほおずき市」は7月に開催され、ほおずき鉢植えが並びます。江戸時代から続く夏のイベントで、期間中は縁日も楽しめます。
ホオズキを使った特別なプレゼント
透かし加工を施したホオズキをガラスケースに入れるなど、アート作品として贈るとユニークなギフトになります。
ホオズキの栽培と注意点

ホオズキの育て方と管理方法
春に苗を植え、日当たりの良い場所で管理します。水やりは土が乾いたらたっぷりと。支柱で倒伏防止をします。
ホオズキを育てる際の注意点
カメムシやアブラムシがつきやすく、葉脈を食害されることがあります。連作障害にも注意。
ホオズキの自然美とその観察方法
開花から果実の色づきまでの変化、透かしホオズキへの移行など、季節ごとの表情を観察するのも魅力です。
ホオズキの食用と利用方法
ホオズキの果実の特徴と用途
観賞用は苦味と毒性があり食用不可ですが、食用ほおずき(ストロベリートマト)は甘酸っぱく生食や菓子に利用可能です。
ホオズキを使ったジャムの作り方
食用品種を砂糖と煮詰め、レモン汁を加えると鮮やかなオレンジ色のジャムになります。
ホオズキの生薬としての利用
古くは根や果実を乾燥させ、生薬「酸漿(さんしょう)」として咳止めや利尿に用いられました。
英語でのホオズキの表現
ホオズキの英名とその語源
“Chinese lantern” は提灯の形が由来。英語圏では観賞植物として親しまれています。
ホオズキに関連する英語の表現
フランス語では “Amour en cage(檻の中の愛)” と呼ばれ、恋愛の象徴として扱われます。
ホオズキの他は?日本で人気の花々
以下、日本で人気の高い花を10種類、それぞれの魅力や良さを含めてご紹介します。
- チューリップ
春を代表する花で、色や品種が豊富。赤・黄・ピンク・紫など多彩な色彩が揃い、ガーデニングや切り花としても人気です。見た目の可愛らしさと手軽な栽培が魅力。 - 薔薇(バラ)
「花の女王」と称されるほど華やかで香りも豊か。色ごとに異なる花言葉を持ち、愛や情熱、感謝を表す贈り物として定番です。品種のバリエーションとアレンジの幅広さが魅力。 - 桜(サクラ)
日本の春の象徴。短期間しか咲かない儚さと、満開時の圧倒的な美しさが人々を魅了します。花見文化をはじめ、季節の風物詩として全国で親しまれています。 - 胡蝶蘭(コチョウラン)
豪華で長持ちする花姿が特徴。開店祝いや就任祝いなど、お祝いのギフトとして非常に人気。蝶が舞うような優雅な形と高級感が魅力です。 - 向日葵(ヒマワリ)
夏を象徴する明るく元気な花。大輪の黄色い花は見ているだけで気分を明るくし、ポジティブなエネルギーを与えてくれます。庭や花畑での観賞も人気。 - 紫陽花(アジサイ)
梅雨の時期に咲く花で、色の変化を楽しめるのが特徴。土壌のpHによって青やピンクに変わるため、同じ株でも年ごとに表情が違うのが魅力です。 - 菊(キク)
古くから日本文化に根付いた花で、長寿や高貴さを象徴。仏花としてだけでなく、近年は洋風アレンジやガーデニングにも用いられます。花持ちの良さも人気の理由です。 - 百合(ユリ)
清楚で香り高い花姿が魅力。カサブランカなどの大輪種は存在感抜群で、ブライダルや特別な日の贈り物に選ばれます。色や香りの種類も多彩。 - 牡丹(ボタン)
「花の王」とも呼ばれる豪華な花。大輪で華やかな姿は、和風庭園や生け花で高く評価されています。春の短い期間だけ咲く希少性も魅力。 - 梅(ウメ)
早春に咲く香り高い花で、寒さの中に咲く姿が凛として美しい。花の観賞だけでなく、実を梅干しや梅酒に利用できる実用性も人気の理由です。
まとめ
ホオズキの花言葉を振り返る
偽り、ごまかし、欺瞞という花言葉の由来は外見と中身のギャップ。一方で自然美、心の平安という前向きな意味もあります。
ホオズキの魅力を感じるシーン
夏の風物詩としての観賞、お盆の飾り、ギフト、アート作品、そして季節のイベント。ホオズキは日本の四季や文化に深く根付いた植物です。
ライター紹介 Writer introduction
Sato君
花屋で働いてた日本男児(O型) コピーライターの経験も活かし花に関して、わかりやすく&信ぴょう性がある記事作りを心掛けながら配信中。 instagramでは「動く!4コマ漫画~花言葉劇場」を投稿しています。